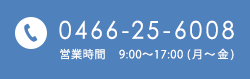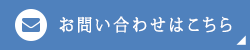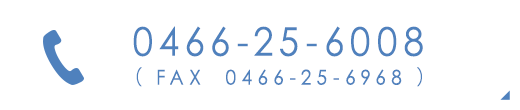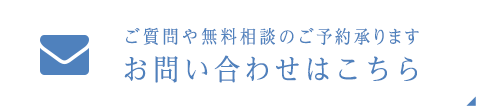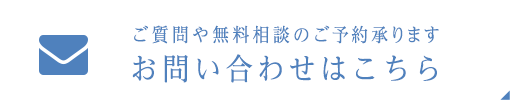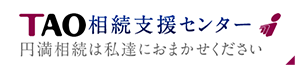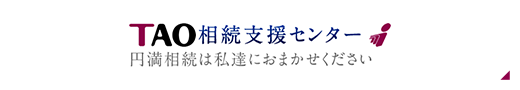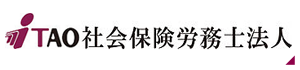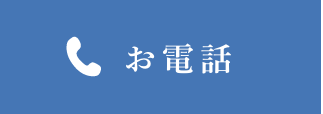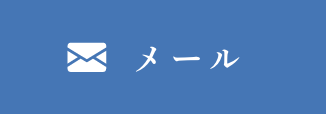東京税理士会が実施した2012年度「税務調査アンケート」結果(有効回答数1701会員)によると、税務調査のあった件数は3153件で、このうち「通知」があったのは3019件(95.8%)、「通知なし」(当日、前日通知を含む)が134件(4.2%)だった。
納税者のみに通知があったのが「7日以上前」305件(9.7%)、「2~6日前」12件(0.4%)、税理士に通知があったのが「7日以上前」2569件(81.5%)、「2~6日前」133件(4.2%)だった。
調査理由の開示については、回答のあった2954件のうち「通知あり」が2631件。このうち、「理由開示を求めたら回答あり」が699件で26.6%、「求めたが回答なし」が237件で9.0%、「求めなかった」は1695件で64.4%。また、「通知なし」323件のうち、「理由開示を求めなかった」が238件で73.7%と、全体では調査理由の開示を求めなかった会員は昨年同様多い。
調査日数では、回答のあった2973件中「1日」で終了したものが599件で20.1%、「2日」が1509件で50.8%と、1~2日で終了したものが全体の7割を超えている。「3~4日」は548件で18.4%、「5日以上」が317件で10.7%と、5日以上の割合は昨年同様1割を超えている。調査内容については、調査件数3153件のうち、「反面調査」が315件で10.0%を占める。調査内容は、「帳簿・証憑」(2548件、80.8%)が基本で、次いで「現金・預金」(785件、24.9%)となっている。
2012.12.11更新
【TAO通信】源泉所得税の来年からの変更点
来年1月から源泉所得税に係る税務処理が色々変わるので注意が必要となる。
まず、復興所得税の創設がある。復興特別所得税は、2013年1月から37年12月までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額の復興特別所得税を併せて徴収する。例えば、報酬・料金として87万6543円を所得税率10%で支払った場合、「87万6543円×10.21%(合計税率)=8万9495.0403円(1円未満切捨て)」で8万9495円が源泉徴収税額となる。
次に、給与所得控除額については、現行は給与等の収入金額に応じて定められており、例えば、1000万円を超える場合は、それ以降の収入金額に制限なく「収入金額×5%+170万円」で算出した額を収入金額から"青天井"で差し引くことができたが、2013年分以後の所得税については、給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、「245万円」の定額とするという制限が設けられる。また、退職所得課税については、勤続年数5年以下の特定の法人役員等(法人役員に相当する公務員・議員を含む)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が、2013年分以後の所得税について廃止される。
上記の給与所得控除の見直しや退職所得課税の見直しは、個人住民税にも反映され、給与所得控除は2014年度分以後、退職所得課税は2013年1月1日以後にそれぞれ適用される。
まず、復興所得税の創設がある。復興特別所得税は、2013年1月から37年12月までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額の復興特別所得税を併せて徴収する。例えば、報酬・料金として87万6543円を所得税率10%で支払った場合、「87万6543円×10.21%(合計税率)=8万9495.0403円(1円未満切捨て)」で8万9495円が源泉徴収税額となる。
次に、給与所得控除額については、現行は給与等の収入金額に応じて定められており、例えば、1000万円を超える場合は、それ以降の収入金額に制限なく「収入金額×5%+170万円」で算出した額を収入金額から"青天井"で差し引くことができたが、2013年分以後の所得税については、給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、「245万円」の定額とするという制限が設けられる。また、退職所得課税については、勤続年数5年以下の特定の法人役員等(法人役員に相当する公務員・議員を含む)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が、2013年分以後の所得税について廃止される。
上記の給与所得控除の見直しや退職所得課税の見直しは、個人住民税にも反映され、給与所得控除は2014年度分以後、退職所得課税は2013年1月1日以後にそれぞれ適用される。
投稿者:
2012.12.11更新
【TAO通信】株主優待導入企業が過去最高の28%
株主の楽しみは、高い配当はもちろんだが、その次には株主優待の商品や優待券などを心待ちにするのが株主に共通のお楽しみというもの。
その株主優待の導入率は今年10月時点で1042社、28%に達し、過去最高を記録したことが野村インベスター・リレーションズ(IR)の調べで分かった。それまでは2008年の1064社が最高で、その後、リーマンショックの影響で株式市場が低迷、2010年には1000社まで落ち込んだが、後半には持ち直し上昇へ転じた。
上場企業にとっての悩みは一向に回復しない株式市場だ。したがい企業業績も上向かない中では配当にお金を回す余裕はない。そのことは株主に理解してもらおうと努力する一方で、新規の個人投資家も呼びこみたいのも本音なのだ。
同時に株主は、その企業のファンであり、消費者でもある。そこに「株主を長くつなぎ留めたい」という企業側の思惑がある。
ただしここ数年の傾向として優待内容をコスト削減で見直す動きも出ている。野村IRの調べでは優待品・券を配る回数を年2回から1回に減らしたり、数量を減らしたりする企業も目立ち、全部で「見直し企業」は158社あったという。
今年の特徴は株主優待を新設・再開した有名企業が目立ったことだ。富士フィルムHDは、自社化粧品のサンプルキットで個人株主増を狙う。また、日本航空は搭乗割引券(50%)を3年以上の長期保有者に上乗せ配布した。
その株主優待の導入率は今年10月時点で1042社、28%に達し、過去最高を記録したことが野村インベスター・リレーションズ(IR)の調べで分かった。それまでは2008年の1064社が最高で、その後、リーマンショックの影響で株式市場が低迷、2010年には1000社まで落ち込んだが、後半には持ち直し上昇へ転じた。
上場企業にとっての悩みは一向に回復しない株式市場だ。したがい企業業績も上向かない中では配当にお金を回す余裕はない。そのことは株主に理解してもらおうと努力する一方で、新規の個人投資家も呼びこみたいのも本音なのだ。
同時に株主は、その企業のファンであり、消費者でもある。そこに「株主を長くつなぎ留めたい」という企業側の思惑がある。
ただしここ数年の傾向として優待内容をコスト削減で見直す動きも出ている。野村IRの調べでは優待品・券を配る回数を年2回から1回に減らしたり、数量を減らしたりする企業も目立ち、全部で「見直し企業」は158社あったという。
今年の特徴は株主優待を新設・再開した有名企業が目立ったことだ。富士フィルムHDは、自社化粧品のサンプルキットで個人株主増を狙う。また、日本航空は搭乗割引券(50%)を3年以上の長期保有者に上乗せ配布した。
投稿者:
2012.12.05更新
【TAO通信】中小企業、M&Aで事業承継に活路
中小企業にとって自社の経営状況が順調であればあるほど後継者選びは悩ましい。経営者が60歳代の団塊世代なら引退と承継の文字がちらつく。帝国データバンクの調査では全国の年商100億円未満の39万7000社のうち26万5000社(約67%)は「後継者不在」と答えている。
これまでの事業承継の手法の多くは「親族への承継」で、次に従業員や外部人材への「親族外承継」、3番目に「M&A(合併・買収)」が使われていたが、それぞれの手法には一長一短がある。特にM&Aには「会社を売る」というイメージがつきまとい経営者の敗北感を拭い切れなかった。M&Aは保有株売却で創業者利益を確保しやすいが、事業好調が最低条件だ。
しかしリーマンショック―海外進出―円高株安―従業員高齢化―大震災等で経営環境が激変した。親族承継は「苦労を背負い込むだけ」と子供側が敬遠する。経営者自身は、自らが立っている業種の将来性と価値を厳密に査定しはじめた。その証拠に、日本M&Aセンターの今年3月期の仲介の成約件数(売・買の案件合計)は前期比24%増の194件と過去最高だった。
みずほ総合研究所は事業承継を経験した中小企業757社に調べたところ「生え抜き役員や外部人材の登用、それにM&Aというように、社内に候補者を早くから選び教育する、外部人材を社長自身がスカウトするなど、様々な手法の組み合わせで承継している」と分析した。
これまでの事業承継の手法の多くは「親族への承継」で、次に従業員や外部人材への「親族外承継」、3番目に「M&A(合併・買収)」が使われていたが、それぞれの手法には一長一短がある。特にM&Aには「会社を売る」というイメージがつきまとい経営者の敗北感を拭い切れなかった。M&Aは保有株売却で創業者利益を確保しやすいが、事業好調が最低条件だ。
しかしリーマンショック―海外進出―円高株安―従業員高齢化―大震災等で経営環境が激変した。親族承継は「苦労を背負い込むだけ」と子供側が敬遠する。経営者自身は、自らが立っている業種の将来性と価値を厳密に査定しはじめた。その証拠に、日本M&Aセンターの今年3月期の仲介の成約件数(売・買の案件合計)は前期比24%増の194件と過去最高だった。
みずほ総合研究所は事業承継を経験した中小企業757社に調べたところ「生え抜き役員や外部人材の登用、それにM&Aというように、社内に候補者を早くから選び教育する、外部人材を社長自身がスカウトするなど、様々な手法の組み合わせで承継している」と分析した。
投稿者:
2012.12.05更新
【TAO通信】国税庁、初めて贈与税事績を公表
国税庁のまとめによると、今年6月までの1年間(2011事務年度)における相続税の実地調査では、無申告事案について1409件実施し、うち932件から1213億円の申告漏れ課税価格を把握したが、申告漏れ等の非違件数、金額は過去10年間で最も多かった。
一方で、相続税の補完税である贈与税についても、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施しており、このほど、初めて贈与税に係る調査事績を公表した。
それによると、2011事務年度は5671件(前事務年度比16.2%増)の実地調査を行い、うち94%に当たる5331件(同17.1%増)に申告漏れ等の非違があり、申告漏れ課税価格280億円(同1.7%減)を把握、79億円(同13.4%減)を追徴課税している。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は494万円(同15.4%減)で追徴税額は140万円(同25.5%減)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.5%が無申告事案であることだ。
申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約177億円(構成比63.3%)で6割強を占め、次いで「有価証券」が約25億円、「土地」が約22億円、「家屋」が約3億円となり、生命保険金や金地金などといった「その他」が約52億円だ。
「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。
一方で、相続税の補完税である贈与税についても、無申告事案を中心に、積極的な調査を実施しており、このほど、初めて贈与税に係る調査事績を公表した。
それによると、2011事務年度は5671件(前事務年度比16.2%増)の実地調査を行い、うち94%に当たる5331件(同17.1%増)に申告漏れ等の非違があり、申告漏れ課税価格280億円(同1.7%減)を把握、79億円(同13.4%減)を追徴課税している。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は494万円(同15.4%減)で追徴税額は140万円(同25.5%減)となる。
贈与税で問題なのは、贈与税の申告漏れ等非違件数の82.5%が無申告事案であることだ。
申告漏れ財産の内訳をみると、「現金・預貯金等」が約177億円(構成比63.3%)で6割強を占め、次いで「有価証券」が約25億円、「土地」が約22億円、「家屋」が約3億円となり、生命保険金や金地金などといった「その他」が約52億円だ。
「現金・預貯金等」の贈与は、税務当局にばれまいと高をくくっている納税者が多いことを裏付ける。
投稿者:
2012.11.29更新
【TAO通信】法人調査の4割は無所得申告法人
今年6月までの1年間(2011事務年度)における法人の黒字申告割合は25.9%と4年ぶりに増加したが、低水準が続いており7割強の法人が赤字だ。このような状況に便乗して実際は黒字なのに赤字を装う企業が後を絶たない。
2011事務年度中に法人税の実地調査をした12万9件のうち4割強にあたる5万5千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強の約6千社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
調査結果によると、実地調査した5万5千件のうち約7割にあたる3万8千件から総額6104億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税額70億円を含む356億円の税額を追徴した。調査1件あたりの申告漏れ所得は1103万円となる。また、実施調査したうちの22.9%の1万3千件は仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額総額は1503億円にのぼった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得は1184万円。
2011事務年度の無所得申告法人調査は、前年度に比べ6.0%増の実地調査を行い、申告漏れ件数は4.0%増、不正計算のあった件数は1.1%増となった。この結果、黒字となった法人が約6千社あったわけだが、調査で把握された1件あたりの申告漏れ所得1103万円は、前年度から12.7%減少したものの、法人全体の平均914万円を大幅に上回る。ここに、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する背景がある。
2011事務年度中に法人税の実地調査をした12万9件のうち4割強にあたる5万5千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強の約6千社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
調査結果によると、実地調査した5万5千件のうち約7割にあたる3万8千件から総額6104億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税額70億円を含む356億円の税額を追徴した。調査1件あたりの申告漏れ所得は1103万円となる。また、実施調査したうちの22.9%の1万3千件は仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額総額は1503億円にのぼった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得は1184万円。
2011事務年度の無所得申告法人調査は、前年度に比べ6.0%増の実地調査を行い、申告漏れ件数は4.0%増、不正計算のあった件数は1.1%増となった。この結果、黒字となった法人が約6千社あったわけだが、調査で把握された1件あたりの申告漏れ所得1103万円は、前年度から12.7%減少したものの、法人全体の平均914万円を大幅に上回る。ここに、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する背景がある。
投稿者:
2012.11.29更新
【TAO通信】8年後には女性管理職30%目標
今後深刻な人口減少が予想される中、活力ある社会を実現するためには女性の活躍を推進することと高齢者の定年延長が鍵となる。最近、EU欧州委員会がEU加盟国の上場企業に対し、2020年までに非常勤役員の4割を女性が占めるよう義務付ける法案をまとめ提示したという。
もう一つは経済協力開発機構(OECD)が年金に関する報告書を公表した。各国政府は年金システムを持続可能な制度にするため、平均寿命の延びに合わせ、年金支給年齢を遅らせる必要があると主張。このため支給開始年齢を67歳以上に引き上げたり、計画中の国がOECD加盟国の約4割に当たる13カ国あると分析した。
OECDの動きには日本は負い目がある。日本の女性管理職比率は世界的に見ても非常に低いことが悪評で、それが男女間の賃金水準の違いの主因である。日本政府は2020年までに女性管理職比率目標を30%に置き、達成されると賃金水準差は世界平均並みとなるが、これは疑問だ。
対策として女性の管理職登用のためには、長時間労働の是正や新卒採用偏重主義、非正規と正規の間の格差縮小といった日本の労働市場が抱える根本的な問題に取り組むことが重要であるというが、正論であっても実行力は無力だ。
一方、日本は年金支給年齢を67歳以上に引き上げる国に日本は入っていない。OECDは「子供や孫が適切な年金制度を享受するには、大胆な行動が求められる」と主張している。
もう一つは経済協力開発機構(OECD)が年金に関する報告書を公表した。各国政府は年金システムを持続可能な制度にするため、平均寿命の延びに合わせ、年金支給年齢を遅らせる必要があると主張。このため支給開始年齢を67歳以上に引き上げたり、計画中の国がOECD加盟国の約4割に当たる13カ国あると分析した。
OECDの動きには日本は負い目がある。日本の女性管理職比率は世界的に見ても非常に低いことが悪評で、それが男女間の賃金水準の違いの主因である。日本政府は2020年までに女性管理職比率目標を30%に置き、達成されると賃金水準差は世界平均並みとなるが、これは疑問だ。
対策として女性の管理職登用のためには、長時間労働の是正や新卒採用偏重主義、非正規と正規の間の格差縮小といった日本の労働市場が抱える根本的な問題に取り組むことが重要であるというが、正論であっても実行力は無力だ。
一方、日本は年金支給年齢を67歳以上に引き上げる国に日本は入っていない。OECDは「子供や孫が適切な年金制度を享受するには、大胆な行動が求められる」と主張している。
投稿者:
2012.11.22更新
【TAO通信】法人の申告漏れ総額は1兆円強
国税庁が発表した今年6月までの1年間(2011事務年度)における法人税調査事績によると、不正計算が想定されるなど調査必要度の高い12万9千法人を実地調査した結果、うち71%にあたる9万2千件から前年度に比べ6.4%減の総額1兆1749億円の申告漏れを見つけた。加算税額336億円を含む2175億円を追徴。1件あたりの申告漏れは914万円となる。申告漏れ所得金額総額及び追徴税額は26年ぶりの低水準となった。
また、調査した19.6%(不正発見割合)にあたる2万5千件が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は3052億円。1件あたりの不正脱漏所得は1212万円となる。
不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が52.6%で10年連続のワースト1位となった。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位(唯一2001年度がワースト2位)という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、「廃棄物処理」(33.1%)、「パチンコ」(31.9%)、「自動車修理」(31.0%)と続く。
一方、1件あたりの不正脱漏所得金額が大きい10業種では、1位は「パチンコ」の4247万円で2年連続のトップ、以下、「その他の娯楽」(2695万円)、「医薬品」(2586万円)、「水運」(2583万円)、「鉄鋼製造」(2516万円)と続き、第6位に、不正発見割合でワースト1位の「バー・クラブ」が2155万円で登場した。
また、調査した19.6%(不正発見割合)にあたる2万5千件が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は3052億円。1件あたりの不正脱漏所得は1212万円となる。
不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が52.6%で10年連続のワースト1位となった。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位(唯一2001年度がワースト2位)という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、「廃棄物処理」(33.1%)、「パチンコ」(31.9%)、「自動車修理」(31.0%)と続く。
一方、1件あたりの不正脱漏所得金額が大きい10業種では、1位は「パチンコ」の4247万円で2年連続のトップ、以下、「その他の娯楽」(2695万円)、「医薬品」(2586万円)、「水運」(2583万円)、「鉄鋼製造」(2516万円)と続き、第6位に、不正発見割合でワースト1位の「バー・クラブ」が2155万円で登場した。
投稿者:
2012.11.22更新
【TAO通信】通信販売で全国の接骨院市場開拓
W・ディズニーは生前、数多くのマーケティング語録を残している。中でも珠玉は「ディズニーランドに完成はない、お客様の欲望に際限はないし、変化に対応しなければならない」というもので、今も陳腐化することはない。
コルセット、サポーターなどの製造販売を手掛けるダイヤ工業(岡山市)は昭和38年設立。ミシンで女性用バッグなどを作っていたが、取引先の倒産で行き詰る。これが「下請けからメーカー志向へ」と発想転換する契機となった。 間もなく腰痛用の牽引器で急成長している会社から声がかかる。知人は「幅が広くて固い」コルセットを使っていた。この幅を狭くすると好評だった。これでコルセット製造に特化する方向を決めたが販路が広がらない。病院は敷居が高く、薬局は取引条件が合わないのだ。
そんな時、接骨院の先生から「既成品では患者の体型や症状に応じて自由に商品が選べず、治療効果が上がらない」と聞いた。これでニッチな市場である接骨院に販路を絞ることにし、最初はイラストを手書きで描いたハガキを送る「手作りの通販」から始めた。
全国に接骨院は約4万箇所、同社の通信販売による取引先はその6割強に及ぶ。製品は接骨院の先生を通じて患者に渡す、いわゆるB TO Bで接骨院の千差万別のニーズに丁寧に応えて成長、平成10年からは毎年新卒採用を開始、平均年齢は現在28.5歳と、さらに完成をめざす。
コルセット、サポーターなどの製造販売を手掛けるダイヤ工業(岡山市)は昭和38年設立。ミシンで女性用バッグなどを作っていたが、取引先の倒産で行き詰る。これが「下請けからメーカー志向へ」と発想転換する契機となった。 間もなく腰痛用の牽引器で急成長している会社から声がかかる。知人は「幅が広くて固い」コルセットを使っていた。この幅を狭くすると好評だった。これでコルセット製造に特化する方向を決めたが販路が広がらない。病院は敷居が高く、薬局は取引条件が合わないのだ。
そんな時、接骨院の先生から「既成品では患者の体型や症状に応じて自由に商品が選べず、治療効果が上がらない」と聞いた。これでニッチな市場である接骨院に販路を絞ることにし、最初はイラストを手書きで描いたハガキを送る「手作りの通販」から始めた。
全国に接骨院は約4万箇所、同社の通信販売による取引先はその6割強に及ぶ。製品は接骨院の先生を通じて患者に渡す、いわゆるB TO Bで接骨院の千差万別のニーズに丁寧に応えて成長、平成10年からは毎年新卒採用を開始、平均年齢は現在28.5歳と、さらに完成をめざす。
投稿者:
2012.11.14更新
【TAO通信】世帯調査で個人年金加入が微増中
1965年(昭和40年)から3年毎に行っている「生命保険に関する全国実態調査」は全国の世帯員2人以上の家庭を対象にした世帯調査。この中から最近増加傾向にあるとされる「個人年金保険の加入状況」を紹介しよう。
個人年金保険に加入している世帯は23.4%(前回21年度調査22.8%)で、確かに微増した。約4世帯に1世帯が個人年金保険に加入している。加入世帯の基本年金額(世帯主と配偶者の合計)は平均117.2万円(前回111.9万円)で、1カ月換算では約10万円を受け取る計算だ。
個人年金保険の加入世帯について、世帯員別の加入割合をみると、世帯主は66.8%(前回66.2%)、配偶者は59.0%(前回58.7%)。
次に関心の高いのは、「何歳から受け取る?」「どのくらいの期間受け取るか?」。調査結果では「60歳から受給開始」が世帯主32.1%、配偶者29.3%でそれぞれトップ、「65歳から受給開始」が世帯主26.6%、配偶者22.0%と続く。
年金の受給期間は「10年間」が世帯主43.5%、配偶者38.9%と、ともに最も多くなっている。背景に公的年金への不満が原因としてある。
調査する生命保険文化センターでは「何歳から受け取るのか、どのくらいの期間受け取るのかを把握していない人も多い」と注意する。調査では、両方の把握漏れは平均で世帯主26%、配偶者35%と多かった。「せっかく加入している個人年金だからこそ大事にしたい」と話す。
個人年金保険に加入している世帯は23.4%(前回21年度調査22.8%)で、確かに微増した。約4世帯に1世帯が個人年金保険に加入している。加入世帯の基本年金額(世帯主と配偶者の合計)は平均117.2万円(前回111.9万円)で、1カ月換算では約10万円を受け取る計算だ。
個人年金保険の加入世帯について、世帯員別の加入割合をみると、世帯主は66.8%(前回66.2%)、配偶者は59.0%(前回58.7%)。
次に関心の高いのは、「何歳から受け取る?」「どのくらいの期間受け取るか?」。調査結果では「60歳から受給開始」が世帯主32.1%、配偶者29.3%でそれぞれトップ、「65歳から受給開始」が世帯主26.6%、配偶者22.0%と続く。
年金の受給期間は「10年間」が世帯主43.5%、配偶者38.9%と、ともに最も多くなっている。背景に公的年金への不満が原因としてある。
調査する生命保険文化センターでは「何歳から受け取るのか、どのくらいの期間受け取るのかを把握していない人も多い」と注意する。調査では、両方の把握漏れは平均で世帯主26%、配偶者35%と多かった。「せっかく加入している個人年金だからこそ大事にしたい」と話す。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)