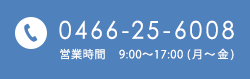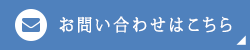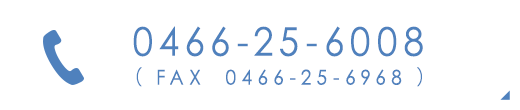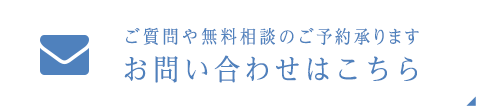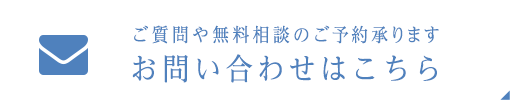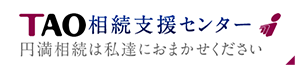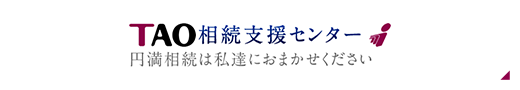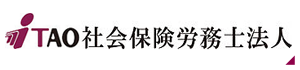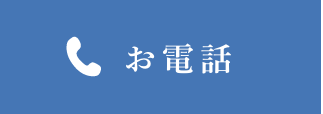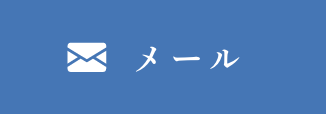平成24年10月25日(木)、平成24年度第5回TAO経営塾を開催いたします。
今回は、社会保険労務士で㈱横浜賃金労務管理オフィス代表取締役 阿部毅様をお招きし、今後の社会環境や経済変化への柔軟な対応し、業績を上げていくための給与体系構築のノウハウについて実際の成功事例をもとに分かりやすく解説していただきます。
ご参加希望の方は当法人まで電話もしくはメールにてお問い合わせください。
【テーマ】
業績を上げるための賃金セミナー
~これなら業績が上がる!給与制度の作り方~
【日時】
平成24年10月25日(木)18時半~20時
【場所】
TAO税理士法人 セミナールーム
【参加費】
1,000円/1人
【講師】
株式会社横浜賃金労務管理オフィス 代表取締役 阿部毅 様 (社会保険労務士)
2012.10.12更新
TAOゴルフコンペを開催
10月10日、晴天のもとTAOゴルフコンペを相模カンツリー倶楽部にて開催しました。毎年この時期に開催しており、今年ではや8回目。34名の方にご参加いただき、楽しい時間を過ごすことができました。


投稿者:
2012.10.12更新
10年後、目指すべき企業像は何か
日本生命保険の35回目となる「ニッセイ景況アンケート調査」によると、多くの企業が10年後の日本経済と自社の経営は現状より厳しくなると認識すると同時に、その時代にあった企業像を構築し難局に対応しようとしていることが明らかとなった。10年後の日本の経済成長に対して悲観的な見通しを持つ企業は8割を上回っている。自社の経営でも10年後の経営が厳しくなると考える企業は59%と過半数を占めた。ただしこのうち53%は「どちらかといえば厳しくなる」と穏やかな悪化を予測した。
今後懸念されるのは「国内市場の低迷」や「人口減少・少子高齢化による需要減少」などで70%が認める。したがい多くの企業は高成長を望むのではなく、4割くらいの企業で、現在の事業規模の維持(安定経営)や高収益企業を目指そうとしている。次ぎに「グローバル展開企業」「地域密着・地域貢献企業」「専門分野特化企業」と続く。高成長を望むのは大・中小企業ともわずか10%を超えた程度だった。
今後10年間の経営課題として、製造業では「商品開発力の向上」「事業のグローバル化」が、非製造業では「人材育成・後継者問題」「新規事業の開拓」が重要になると指摘。日本経済の活力維持策には何が重要か?では、今後の日本経済を楽観的か悲観的に見るかで、期待する活力維持策の内容が分かれた。企業経営が大きな曲がり角に立つことが背景にある。
今後懸念されるのは「国内市場の低迷」や「人口減少・少子高齢化による需要減少」などで70%が認める。したがい多くの企業は高成長を望むのではなく、4割くらいの企業で、現在の事業規模の維持(安定経営)や高収益企業を目指そうとしている。次ぎに「グローバル展開企業」「地域密着・地域貢献企業」「専門分野特化企業」と続く。高成長を望むのは大・中小企業ともわずか10%を超えた程度だった。
今後10年間の経営課題として、製造業では「商品開発力の向上」「事業のグローバル化」が、非製造業では「人材育成・後継者問題」「新規事業の開拓」が重要になると指摘。日本経済の活力維持策には何が重要か?では、今後の日本経済を楽観的か悲観的に見るかで、期待する活力維持策の内容が分かれた。企業経営が大きな曲がり角に立つことが背景にある。
投稿者:
2012.10.12更新
11年分民間の平均給与は409万円
国税庁がこのほど発表した2011年分民間給与の実態統計調査によると、2011年1年間を通して民間企業に勤めた給与所得者の平均給与は409万円で、前年に比べ0.7%(3万円)減少した。平均給与は2年ぶりに減少した。同調査は、全国の約2万事業所、約27万6千人の数値をもとに推計したもの。
調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比0.3%増の4566万人だった。その平均給与409万円の内訳は、平均給料・手当が1.2%減の349万7千円と2年ぶりの減少、賞与は2.1%増の59万3千円と2年連続の増加となった。
男女別の平均給与は、男性が前年比0.7%減の503万8千円、女性が0.5%減の267万9千円だった。なお、1年を通じて勤務した給与所得者総数は4566万人のうち、男性は同0.1%増の2731万人、女性は同0.6%増の1835万人と2年連続で過去最多を更新した。給与総額は186兆7459億円で、同0.4%減と2年ぶりに減少した。
給与所得者4566万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している人は全体の84.4%を占める3853万人で、前年より2.6%増加した。また、その納税額は7兆5529億円、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.37%だった。
納税額(源泉徴収税額)は前年に比べ4.2%増と2年連続で増加したが、これは、子ども手当の導入に伴い所得税の扶養控除の一部が廃止・縮小されたためとみられている。
調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比0.3%増の4566万人だった。その平均給与409万円の内訳は、平均給料・手当が1.2%減の349万7千円と2年ぶりの減少、賞与は2.1%増の59万3千円と2年連続の増加となった。
男女別の平均給与は、男性が前年比0.7%減の503万8千円、女性が0.5%減の267万9千円だった。なお、1年を通じて勤務した給与所得者総数は4566万人のうち、男性は同0.1%増の2731万人、女性は同0.6%増の1835万人と2年連続で過去最多を更新した。給与総額は186兆7459億円で、同0.4%減と2年ぶりに減少した。
給与所得者4566万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している人は全体の84.4%を占める3853万人で、前年より2.6%増加した。また、その納税額は7兆5529億円、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.37%だった。
納税額(源泉徴収税額)は前年に比べ4.2%増と2年連続で増加したが、これは、子ども手当の導入に伴い所得税の扶養控除の一部が廃止・縮小されたためとみられている。
投稿者:
2012.10.03更新
職種別の転職条件の必須資格とは
総務省「労働力調査詳細集計」によると、大震災1年前の2010年の就業者数は約6200万人だったが、男性は製造業、建設業で減少、女性も減少はしたが、医療福祉関連業で増加した。
リーマンショック後、転職者数は男女合わせ2008年から10年まで3年間連続して減少して、特に10年は300万人を割って282万人と大幅に減った。これは景気低迷で労働市場が流動化せず転職にブレーキがかかったのが原因とみられる。
11年以降は大震災の影響と電気機器などの海市場での低迷でリストラが加速し失業者、転職者とも増えるのは確実だ。
一方、就職情報誌が調べた職種別の転職条件の必須資格の第1位は「普通自動車免許第一種」で営業、介護で重視。2位「薬剤師」、3位「MR(医薬情報担当者)」と医療系の資格が上位にランクイン。4位の「建築士一級」をはじめ、6位の「建築士二級」、8位の「建築施工管理技士1級」など、医療も建築も士業といわれる国家資格が大半で、難関資格でもある。
「その資格があれば、なお可」(転職に有利)とされる1位は「宅地建物取引主任者」で営業系や不動産系の専門職などで需要が多い。次いで「日商簿記検定2級」も求人が多く資格の定番。今後は人気の英検も必須化しそうだ。
ただし求人側の狙いは「経験重視」(85%)だ。転職者とは即戦力を意味するので「書類内容より実戦能力」と採用担当者は忠告する。
リーマンショック後、転職者数は男女合わせ2008年から10年まで3年間連続して減少して、特に10年は300万人を割って282万人と大幅に減った。これは景気低迷で労働市場が流動化せず転職にブレーキがかかったのが原因とみられる。
11年以降は大震災の影響と電気機器などの海市場での低迷でリストラが加速し失業者、転職者とも増えるのは確実だ。
一方、就職情報誌が調べた職種別の転職条件の必須資格の第1位は「普通自動車免許第一種」で営業、介護で重視。2位「薬剤師」、3位「MR(医薬情報担当者)」と医療系の資格が上位にランクイン。4位の「建築士一級」をはじめ、6位の「建築士二級」、8位の「建築施工管理技士1級」など、医療も建築も士業といわれる国家資格が大半で、難関資格でもある。
「その資格があれば、なお可」(転職に有利)とされる1位は「宅地建物取引主任者」で営業系や不動産系の専門職などで需要が多い。次いで「日商簿記検定2級」も求人が多く資格の定番。今後は人気の英検も必須化しそうだ。
ただし求人側の狙いは「経験重視」(85%)だ。転職者とは即戦力を意味するので「書類内容より実戦能力」と採用担当者は忠告する。
投稿者:
2012.10.03更新
来年からは復興特別所得税を徴収
周知のように、所得税の源泉徴収義務者は、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収する必要がある。
源泉すべき復興特別所得税の額は、源泉すべき所得税の額の2.1%相当額である。源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、「支払金額等×合計税率(%)(所得税率(%)×102.1%)」となる。算出額の1円未満の端数は切り捨てる。
従業員の給与等については、2013年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付すればいいので問題はないだろう(2013年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載されており、税務署からも年末調整の時期に配布予定)。
注意が必要なのは、原稿料や講演料、税理士や弁護士など特定の資格を持つ人に報酬・料金等を支払う際の源泉徴収だ。
現在、原稿料や講演料などを支払う際に源泉徴収する所得税の額の計算は、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20%+10万円」だが、来年1月以降は、復興特別所得税の2.1%が上乗せされるため、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10.21%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円」となる。
源泉すべき復興特別所得税の額は、源泉すべき所得税の額の2.1%相当額である。源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、「支払金額等×合計税率(%)(所得税率(%)×102.1%)」となる。算出額の1円未満の端数は切り捨てる。
従業員の給与等については、2013年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付すればいいので問題はないだろう(2013年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載されており、税務署からも年末調整の時期に配布予定)。
注意が必要なのは、原稿料や講演料、税理士や弁護士など特定の資格を持つ人に報酬・料金等を支払う際の源泉徴収だ。
現在、原稿料や講演料などを支払う際に源泉徴収する所得税の額の計算は、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20%+10万円」だが、来年1月以降は、復興特別所得税の2.1%が上乗せされるため、支払金額が100万円以下の場合は「支払金額×10.21%」、100万円超の場合は「(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円」となる。
投稿者:
2012.09.26更新
太陽光発電事業、屋上貸しで拡大
公共施設や工場、ビルの屋上・屋根を事業者(太陽光発電事業)に貸して行う「屋上貸し発電事業」が自治体と民間事業者とのコンビで普及と実益の市場拡大を生み出そうとしている。きっかけは今年7月、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まったからだ。
9月現在、神奈川県が率先して県立高校、福祉施設、県営住宅など20施設25棟の屋上を貸し出し、高校の場合、使用料として年間30万円が県の収入となる。事業者は公募で4社が選ばれた。20施設全体の発電能力は2214キロワット、年間で496万円が神奈川県の財政を潤す。契約は20年間で、政府の買い取り期間と同じ。市町村にも波及し栃木県足利市が公民館など68施設対象に公募、2事業者を仮選定した。大阪府泉佐野市は16小・中学校対象に事業者を募集。
規模の大きい東京都がこの事業に参入すると拡大が加速するが、太陽光発電普及の新たなビジネスモデルとして研究しているという。普及啓発も自治体の大きな役割だからだ。
一方、民間事業者の課題は現在1キロワット当たり42円の固定買取価格が毎年、原則見直され、元々電気料金に転嫁される仕組みへの対応で、このため事業者の採算が読みにくいとされる。しかしコンビニ程度の広さなら採算がとれるのもこのビジネスの魅力で屋上発電事業(屋根賃貸)は太陽光発電の拡大チャンスになると予想され、新たなビジネスチャンスの到来だ。
9月現在、神奈川県が率先して県立高校、福祉施設、県営住宅など20施設25棟の屋上を貸し出し、高校の場合、使用料として年間30万円が県の収入となる。事業者は公募で4社が選ばれた。20施設全体の発電能力は2214キロワット、年間で496万円が神奈川県の財政を潤す。契約は20年間で、政府の買い取り期間と同じ。市町村にも波及し栃木県足利市が公民館など68施設対象に公募、2事業者を仮選定した。大阪府泉佐野市は16小・中学校対象に事業者を募集。
規模の大きい東京都がこの事業に参入すると拡大が加速するが、太陽光発電普及の新たなビジネスモデルとして研究しているという。普及啓発も自治体の大きな役割だからだ。
一方、民間事業者の課題は現在1キロワット当たり42円の固定買取価格が毎年、原則見直され、元々電気料金に転嫁される仕組みへの対応で、このため事業者の採算が読みにくいとされる。しかしコンビニ程度の広さなら採算がとれるのもこのビジネスの魅力で屋上発電事業(屋根賃貸)は太陽光発電の拡大チャンスになると予想され、新たなビジネスチャンスの到来だ。
投稿者:
2012.09.26更新
税務調査手続き等の先行的取組み
2011年度税制改正において国税通則法等が改正され、税務調査手続きについて現行の運用上の取扱いを法律上明確化するなどの措置が講じられている。今回の改正は、原則として2013年1月1日以後に開始する調査から適用されることになるが、国税庁では、法施行後における税務調査手続き等を円滑かつ適切に実施するため、今年10月1日以後に開始する調査から一部の調査手続きについて先行的に取り組むことを予定している。
先行的に取り組むのは、①事前通知と②修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続きだ。事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとする。
次に、修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。また、調査開始日時等の変更の申出や提出物件の留置き・返還など、その他の税務調査手続き等については、一部の調査手続きを除き、法施行後の調査手続きに準じて、各手続きを実施することとする。
先行的に取り組むのは、①事前通知と②修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続きだ。事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとする。
次に、修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。また、調査開始日時等の変更の申出や提出物件の留置き・返還など、その他の税務調査手続き等については、一部の調査手続きを除き、法施行後の調査手続きに準じて、各手続きを実施することとする。
投稿者:
2012.09.19更新
7月以降は一転、個人消費に陰り
総務省の家計調査(二人以上世帯の実質消費支出4~6月期。7月分速報)が8月末発表された。平均世帯人員3.07人、世帯主の平均年齢57.4歳の消費支出は、1世帯当たり1か月平均286,556円、前年同期比で実質2.7%増。
家計調査消費支出は自分たちの生活の足跡が速報で表される生きのいいデータだ。今年前半は「消費好調」、後半「低調」との予想が出て景気の下降線が懸念される。
まず4~6月は勤労者世帯の実収入実質増加が好調に寄与し前年同期比で実質2.6%増。世帯主とその配偶者の収入など全項目が増加した。
寄与した主な商品・サービスは、自動車等関係費や交通・通信のほか、授業料等や補習教育を含む教育、設備修繕・維持を含む住居、外食や乳卵類を含む食料。また、教養娯楽サービスを含む教養娯楽のほか、電気代を含む光熱・水道や家庭用耐久財も寄与した。
6月の消費は、気温が低く台風・豪雨等の天候不順から外出が減り比較的低調の割合が目立つ。7月には反動増も期待されたが伸び悩んだ。この間、小遣いは減り、ウナギ(蒲焼き)の売上げは前年比50%以上も激減した。
今後の懸念材料はエコカー補助金の終了(10月予定?)で秋~冬の自動車販売の大幅減少は避けられまい。エコ家電も終わり補助金頼みの家計は一苦労だ。消費マインドを刺激するとはいえ真の景気対策の定着とまではいえない。
家計調査消費支出は自分たちの生活の足跡が速報で表される生きのいいデータだ。今年前半は「消費好調」、後半「低調」との予想が出て景気の下降線が懸念される。
まず4~6月は勤労者世帯の実収入実質増加が好調に寄与し前年同期比で実質2.6%増。世帯主とその配偶者の収入など全項目が増加した。
寄与した主な商品・サービスは、自動車等関係費や交通・通信のほか、授業料等や補習教育を含む教育、設備修繕・維持を含む住居、外食や乳卵類を含む食料。また、教養娯楽サービスを含む教養娯楽のほか、電気代を含む光熱・水道や家庭用耐久財も寄与した。
6月の消費は、気温が低く台風・豪雨等の天候不順から外出が減り比較的低調の割合が目立つ。7月には反動増も期待されたが伸び悩んだ。この間、小遣いは減り、ウナギ(蒲焼き)の売上げは前年比50%以上も激減した。
今後の懸念材料はエコカー補助金の終了(10月予定?)で秋~冬の自動車販売の大幅減少は避けられまい。エコ家電も終わり補助金頼みの家計は一苦労だ。消費マインドを刺激するとはいえ真の景気対策の定着とまではいえない。
投稿者:
2012.09.19更新
経産省、2013年度改正要望を公表
経済産業省はこのほど、2013年度税制改正に関する要望を公表し、(1)車体課税の抜本的見直しや研究開発促進税制の拡充等、(2)再エネ・コジュネの導入拡大、省エネ抜本強化等、(3)事業承継の円滑化等を掲げた。
車体課税の抜本的見直しでは、車体課税は取得・保有段階において複数の税が課されており、過大な税負担が自動車ユーザーのクルマ離れ、国内市場低迷の一因となっていることなどから、自動車取得税・自動車重量税について、道路特定財源廃止により課税根拠を喪失していることなどを踏まえ、当分の間として適用されている税率も含め廃止を求めた。
再エネ・コジュネの導入拡大、省エネ抜本強化では、グリーン投資減税の対象設備等の拡充やコージェネレーションに係る固定資産税の課税標準の特例の創設などを掲げた。捨てられている廃熱(未利用エネルギー)を活用するコージェネレーションに係る固定資産税については、課税標準を最初の3年間、課税標準となるべき価格の3分の1に軽減することを求めている。事業承継の円滑化に向けては、納税猶予の適用要件について、親族外承継の対象化や役員退任要件を代表者退任要件に緩和、雇用8割維持要件について、毎年でなく5年間の平均で判定し、未達成の場合は下回った分を納税、5年経過後に納税猶予額を全額免除、などを求めた。また、小規模会社が所有する事業用土地の評価額の80%相当額を、課税価格から減額する特例の創設を要望している。
車体課税の抜本的見直しでは、車体課税は取得・保有段階において複数の税が課されており、過大な税負担が自動車ユーザーのクルマ離れ、国内市場低迷の一因となっていることなどから、自動車取得税・自動車重量税について、道路特定財源廃止により課税根拠を喪失していることなどを踏まえ、当分の間として適用されている税率も含め廃止を求めた。
再エネ・コジュネの導入拡大、省エネ抜本強化では、グリーン投資減税の対象設備等の拡充やコージェネレーションに係る固定資産税の課税標準の特例の創設などを掲げた。捨てられている廃熱(未利用エネルギー)を活用するコージェネレーションに係る固定資産税については、課税標準を最初の3年間、課税標準となるべき価格の3分の1に軽減することを求めている。事業承継の円滑化に向けては、納税猶予の適用要件について、親族外承継の対象化や役員退任要件を代表者退任要件に緩和、雇用8割維持要件について、毎年でなく5年間の平均で判定し、未達成の場合は下回った分を納税、5年経過後に納税猶予額を全額免除、などを求めた。また、小規模会社が所有する事業用土地の評価額の80%相当額を、課税価格から減額する特例の創設を要望している。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)