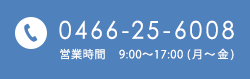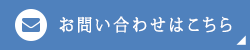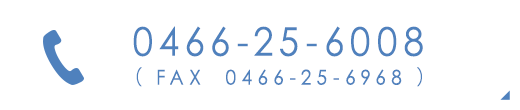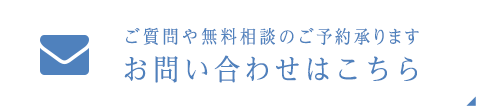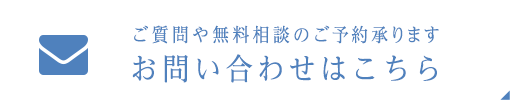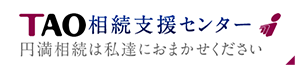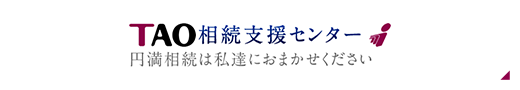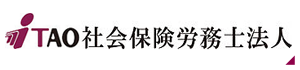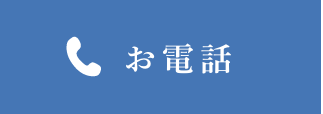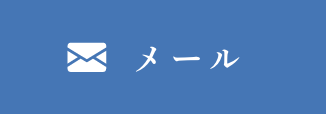税の徴収率向上は地方自治体の尽きない悩み。窓口納付のみならず、口座振替、コンビニ納税、eL-TAXと納税手段の多様化に努めてきたが、近年、急速に導入が進んでいるのが「Pay-Easy(ペイジー)」だ。自治体だけでなく、国や民間企業でも利用が進んでいる。
ペイジーは現金を用意する必要がなく、役所や金融機関に出向かずに、近くにコンビニがなくとも、自宅等から手続きできるのが一番のメリット。窓口とは異なり、第三者に税額を知られる心配もない。
公金取扱サービスがスタートした2004年1月からの10年間で、自治体の導入団体は東京都等21都府県、千葉市・横浜市など9政令市を含む40市区町に広がり、取扱金融機関も都市銀行・地方銀行をほぼ網羅するまでになった。ペイジーの運営・普及にあたる日本マルチペイメント推進協議会・同運営機構によれば、今年度の自治体の公金取扱件数は年間1200万件(対前年度比117%)、取扱金額は1兆4000億円(同110%)になる見込みという。
また、取扱いできる税目や料金は自治体によって異なるが、自動車税・事業税などの府県税、住民税・固定資産税・軽自動車税などの市町村税をはじめ、使用料・手数料、国民健康保険料など幅広いことが特徴だ。役所から届いた納付書にペイジーマークがあればこのシステムを利用できるが、領収書が出ないことが難点。領収書がほしい場合は他の納税手段を利用する必要がある。
2014.04.10更新
【TAO通信】ふるさと納税、件数増でも金額が小口化
ふるさと納税は都道府県や市町村を選んで寄付する。東日本大震災のあった2011年には都道府県と市町村合わせて130億円を記録したが、12年以前の過去5年間で100億円を超えたのは、この2011年だけだ。総務省の調査では、「ふるさと納税」制度を導入した2008年に5万4004件(一部の災害義捐金除く)だった個人の自治体への寄付件数が12年に2.3倍の12万1858件まで増えた。11年も件数は11万件を超えている。
これに対して、寄付額は77億円から96億円へ25%の増加にとどまった。1件あたりの平均寄付額は14万2582円から7万8780円に減った。13年の寄付金は未集計だが小口金額が予想される。
2013年4~11月までの都道府県の受け取った金額のベスト5は、上位から順に鳥取(金額1億2775万円 件数9177)、岩手(7098万円 1439)、福島(4289万円 875)、長野(3680万円 2668)、佐賀(1964万円 798)。5県の共通項には特産品が豊富で被災地が2県入っていること。
ふるさと納税はどこの自治体でも、お礼に特産品の中から1品目選んで送ってくれる仕組みになっている。寄付額が1万円以上なら5千円程度の特産品で対応するところが多い。しかし震災翌年には約50億円も減ったのは、特産品が寄付額に見合わない倹約派が増えたか、純粋に被災地への応援派が減ったか、この税制の地方への税収移管が目的には無理があるのかも?
これに対して、寄付額は77億円から96億円へ25%の増加にとどまった。1件あたりの平均寄付額は14万2582円から7万8780円に減った。13年の寄付金は未集計だが小口金額が予想される。
2013年4~11月までの都道府県の受け取った金額のベスト5は、上位から順に鳥取(金額1億2775万円 件数9177)、岩手(7098万円 1439)、福島(4289万円 875)、長野(3680万円 2668)、佐賀(1964万円 798)。5県の共通項には特産品が豊富で被災地が2県入っていること。
ふるさと納税はどこの自治体でも、お礼に特産品の中から1品目選んで送ってくれる仕組みになっている。寄付額が1万円以上なら5千円程度の特産品で対応するところが多い。しかし震災翌年には約50億円も減ったのは、特産品が寄付額に見合わない倹約派が増えたか、純粋に被災地への応援派が減ったか、この税制の地方への税収移管が目的には無理があるのかも?
投稿者:
2014.04.09更新
【TAO通信】2012年度分の赤字法人割合は70.3%
国税庁が公表した「2012年度分会社標本調査」結果によると、2012年度分の法人数は253万5272社で、前年度より▲1.7%減で3年連続減少した。うち、連結子法人(9288社)を除いた252万5984社のうち、赤字法人は177万6253社で、赤字法人割合は70.3%となり、前年度の2011年度分から2.0ポイント減少したものの、高水準に変わりない。
2012年度分の営業収入金額は、前年度に比べ8.7%増の1386兆1038億円と増加に転じ、黒字法人の営業収入金額は同32.7%増の1018兆1159億円、所得金額も同20.1%増の40兆7636億円と大幅に増加、ともに3年連続の増加となった。
赤字法人割合は高水準だったものの、順調に景気回復を図っている企業との二極化がうかがえる。
一方、2013年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度に比べ0.8%増の2兆9010億円と、6年ぶりに増加に転じたが、過去最高だった1992年分の6兆2078億円に比べほぼ半減している。
営業収入10万円あたりの交際費等支出額は、全体では前年度より17円少ない209円で、資本金1千万円以下の階級が570円と高い一方、資本金が多くなるにつれ減少し、資本金10億円以上では99円と低い。また、業種別にみると、「建設業」が546円、「不動産業」が542円、「サービス業」が417円と高く、一方、「鉱業」が132円、「金融保険業」が136円、「機械工業」が154円と低くなっている。
2012年度分の営業収入金額は、前年度に比べ8.7%増の1386兆1038億円と増加に転じ、黒字法人の営業収入金額は同32.7%増の1018兆1159億円、所得金額も同20.1%増の40兆7636億円と大幅に増加、ともに3年連続の増加となった。
赤字法人割合は高水準だったものの、順調に景気回復を図っている企業との二極化がうかがえる。
一方、2013年3月までの1年間に全国の企業が取引先の接待などに使った交際費は、前年度に比べ0.8%増の2兆9010億円と、6年ぶりに増加に転じたが、過去最高だった1992年分の6兆2078億円に比べほぼ半減している。
営業収入10万円あたりの交際費等支出額は、全体では前年度より17円少ない209円で、資本金1千万円以下の階級が570円と高い一方、資本金が多くなるにつれ減少し、資本金10億円以上では99円と低い。また、業種別にみると、「建設業」が546円、「不動産業」が542円、「サービス業」が417円と高く、一方、「鉱業」が132円、「金融保険業」が136円、「機械工業」が154円と低くなっている。
投稿者:
2014.04.04更新
【TAO通信】推計課税を相続税にも拡大する動き
税務調査は、納税者が申告した所得金額が正しいかどうかを、総勘定元帳や補助簿、各種原始記録と照合し検討を行うことが大原則だが、帳簿の記載の不備や原始書類の保存状況が極めて悪いなどの理由から、納税者の資料では所得金額の検討ができないときは、納税者の生活状況や財産債務の増減、収支の状況、生産量、従業員数、同業他社との比較といった客観的な資料情報から所得金額を推計し、金額を決定する「推計課税」ができる。
現在この推計課税が認められるのは法人税と所得税のみだが、これを相続税にも広げようという動きが国税庁にある。国税庁が独自の意見書として財務省に提出した内容は、「相続開始以前の一定期間中に、被相続人の財産を処分または被相続人が債務を負担したもので、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合は、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設する」というもの。
相続税の推計課税は、国税庁が2012年から3年越しで要望しているというが、3月20日に成立した2014年度税制改正法にも盛り込まれていなかった。しかし、2013年度税制改正において税率構造の見直しや基礎控除の引下げが行われるなど相続税への課税強化路線にあるなか、国税庁が簡単に諦めるとは考えにくく、2015年度税制改正でさらに強気の要望を載せてくる可能性は高い。今後の動きに注目しておく必要がある。
現在この推計課税が認められるのは法人税と所得税のみだが、これを相続税にも広げようという動きが国税庁にある。国税庁が独自の意見書として財務省に提出した内容は、「相続開始以前の一定期間中に、被相続人の財産を処分または被相続人が債務を負担したもので、その使途が客観的に明白でなく、かつ、その合計額が一定金額以上となる場合は、これを相続人が相続したものと推定し、相続税の課税価格に算入する制度を創設する」というもの。
相続税の推計課税は、国税庁が2012年から3年越しで要望しているというが、3月20日に成立した2014年度税制改正法にも盛り込まれていなかった。しかし、2013年度税制改正において税率構造の見直しや基礎控除の引下げが行われるなど相続税への課税強化路線にあるなか、国税庁が簡単に諦めるとは考えにくく、2015年度税制改正でさらに強気の要望を載せてくる可能性は高い。今後の動きに注目しておく必要がある。
投稿者:
2014.03.26更新
【TAO通信】2014年度税制改正法が20日に成立
今国会で審議中だった2014年度税制改正関連法が3月20日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。3月20日の成立は、阪神・淡路大震災の税制上の救済法案の審議の関係もあって異例のスピード成立となった1995年(3月17日成立)に次ぐ戦後2番目の早さとなる。
中心は、通常の年度改正から切り離して2013年10月1日に決定した「秋の大綱」に盛り込まれていた景気浮揚を目的とした企業減税となる。デフレ不況からの脱却と経済再生に向けた財政措置として、(1)復興特別法人税を1年前倒しで廃止する。(2)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して5%以上増加)を、2013・2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016・2017年度は5%以上とする等の見直しを行う。(3)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却または5%税額控除ができる制度(「生産性向上設備投資促進税制」)を創設する。(4)試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の5%)について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率5%~30%)へ改組する。(5)中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却または7%税額控除(資本金3000万円以下の企業は10%)を認める。(6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める、などがある。
中心は、通常の年度改正から切り離して2013年10月1日に決定した「秋の大綱」に盛り込まれていた景気浮揚を目的とした企業減税となる。デフレ不況からの脱却と経済再生に向けた財政措置として、(1)復興特別法人税を1年前倒しで廃止する。(2)所得拡大促進税制について、給与等支給増加割合の要件(現行基準年度と比較して5%以上増加)を、2013・2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016・2017年度は5%以上とする等の見直しを行う。(3)生産性の向上につながる設備(先端設備等)を取得した場合に、即時償却または5%税額控除ができる制度(「生産性向上設備投資促進税制」)を創設する。(4)試験研究費の増加額に係る税額控除制度(現行増加額の5%)について、試験研究費の増加率に応じて税額控除率を引き上げる仕組み(控除率5%~30%)へ改組する。(5)中小企業投資促進税制を拡充し、生産性の向上につながる設備を取得した場合に、即時償却または7%税額控除(資本金3000万円以下の企業は10%)を認める。(6)交際費等の損金不算入制度について、飲食のための支出の50%を損金算入することを認める、などがある。
投稿者:
2014.03.19更新
【TAO通信】税金は支払義務が免除されない債権
個人事業主が自己破産した場合、未納税金の納付義務もなくなるのだろうか。自己破産というのは、全ての借金を支払う義務がなくなることだから、税金も払わなくてよくなると考える向きも多い。
実は、自己破産をし、裁判所から免責決定がおりれば原則として全ての債務が免除されが、一方で例外もあり、非免責債権とされるものについては、例え免責決定がおりたとしても、その支払義務が免除されることはないのだ。
税金はその非免責債権に該当する。非免責債権は破産法253条に列挙されているが、その中に租税等の請求権が挙げられている。
自己破産をし、免責決定がおりたとしてもその支払を免れない債権もあって、税金はその典型ということになる。そのほか、非免責債権とされるものには、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、(4)罰金等の請求権、などがある。
したがって、経営者や個人事業主は未納税金について自己破産の免責決定では消滅しないことに留意し、日頃から計画的に納税資金を貯めていくことが必要となる。万が一支払えない税金がでてきそうな場合には、納税の猶予について国に相談し、分割でも支払っていくことが重要だ。
実は、自己破産をし、裁判所から免責決定がおりれば原則として全ての債務が免除されが、一方で例外もあり、非免責債権とされるものについては、例え免責決定がおりたとしても、その支払義務が免除されることはないのだ。
税金はその非免責債権に該当する。非免責債権は破産法253条に列挙されているが、その中に租税等の請求権が挙げられている。
自己破産をし、免責決定がおりたとしてもその支払を免れない債権もあって、税金はその典型ということになる。そのほか、非免責債権とされるものには、(1)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、(2)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、(3)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権、(4)罰金等の請求権、などがある。
したがって、経営者や個人事業主は未納税金について自己破産の免責決定では消滅しないことに留意し、日頃から計画的に納税資金を貯めていくことが必要となる。万が一支払えない税金がでてきそうな場合には、納税の猶予について国に相談し、分割でも支払っていくことが重要だ。
投稿者:
2014.03.12更新
【TAO通信】交際費等の50%損金算入は4月以後
2014年度税制改正の中で交際費等の損金算入の取扱いが注目されている。改正法案によると、2014年4月1日以後開始事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食のために支出する費用の額の50%相当額まで損金算入できる規定が新設される。
現行法では、まず、法人が、1982年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は全額損金不算入とした上で、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。
2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。
このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。
現行法では、まず、法人が、1982年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額は全額損金不算入とした上で、資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの交際費等の額を損金算入できる特例措置を設け、次に、法人の規模を問わず政令で定める1人当たり5000円以下の飲食費を交際費等から除外することで損金算入できる規定を設けている。
2014年度税制改正では、まず、法人が2014年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は損金不算入とする規定を新設した上で、中小法人については、中小法人の特例と新設の50%基準との選択ができる構成にしている。また、飲食費の5000円基準は今回の改正で見直しはないため継続する。
このため、5000円基準適用の場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を除き、その残りの飲食費の50%相当額が、飲食費に係る損金不算額に、また、5000円基準を適用しない場合は、1人当たり5000円以下の飲食費を含めた飲食費全額の50%相当額が飲食費に係る損金不算入額になることになる。
投稿者:
2014.03.05更新
【TAO通信】2014年度の国民負担率は過去最高
国民負担率とは、国民所得に対する税金や社会保険料(年金・医療費などの保険料)の負担割合。財務省はこのほど、2013年度の実績見込みでは40.6%だった国民負担率が、2014年度予算では1.0ポイント増の41.6%と過去最高となる見通しと発表した。景気回復や消費税率引上げ等に伴い租税負担率が増加し、2年ぶりに前年を上回る。14年度見通しの内訳は、国税が14.5%、地方税が9.6%で租税負担率が24.1%、社会保障負担率は17.5%。
2013年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.8ポイント増(国税0.9ポイント増、地方税は横ばい)、社会保障負担率は0.1ポイント増。社会保障負担は、この統計を開始した1970年以降では最高だった12・13年度(17.4%)をわずかに上回った。
国民負担率を諸外国(11年実績)と比べた場合、アメリカ(30.8%)よりは高いが、フランス(61.9%)、スウェーデン(58.2%)、ドイツ(51.2%)、イギリス(47.7%)などよりは低い。
真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。
財務省によると、2014年度の国民所得(13年度に比べ7万6千円増の370万5千円)に対する財政赤字の割合は、前年度から1.3ポイント減の10.3%となる見通し。この結果、14年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的国民負担率」は、13年度からは0.3ポイント減の51.9%となる見通しだが、引き続き5割を超えている。
2013年度実績見込みに比べ、租税負担率は0.8ポイント増(国税0.9ポイント増、地方税は横ばい)、社会保障負担率は0.1ポイント増。社会保障負担は、この統計を開始した1970年以降では最高だった12・13年度(17.4%)をわずかに上回った。
国民負担率を諸外国(11年実績)と比べた場合、アメリカ(30.8%)よりは高いが、フランス(61.9%)、スウェーデン(58.2%)、ドイツ(51.2%)、イギリス(47.7%)などよりは低い。
真の負担率は、財政赤字という形で将来世代へ先送りしている負担額を加える必要がある。
財務省によると、2014年度の国民所得(13年度に比べ7万6千円増の370万5千円)に対する財政赤字の割合は、前年度から1.3ポイント減の10.3%となる見通し。この結果、14年度の国民負担率に財政赤字を加えた「潜在的国民負担率」は、13年度からは0.3ポイント減の51.9%となる見通しだが、引き続き5割を超えている。
投稿者:
2014.02.26更新
【TAO通信】定期借地権保証金の経済的利益
定期借地権は、1992年8月に施行された新借地借家法に基づいて、当初の契約期間で借地契約が終了し、その後更新がない制度である。
この定期借地権の設定に伴い貸主が預かった保証金を個人的に使ってしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。その際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算され、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入する。
国税庁はこのほど、その適正利率が、2013年分は前年分から0.1ポイント低い0.7%と、前年2012年分の0.8%を下回り過去最低を記録したことを明らかにした。この「適正利率」は各年度の10年長期国債の平均利率によることとされ、2013年の10年長期国債の平均利率が0.72%だったことから「0.7%」としたもの。この取扱いは、1993年分の不動産所得の申告から始まっているが、同年分は4%。それからずいぶん低下したものだ。
この結果、保証金を事業用資金や事業用資産の取得資金として使う場合に、各年分の不動産所得の収入金額と必要経費に算入する利息相当額を算出する「適正利率」は、平均的な長期借入利率のほか0.7%としても差し支えない。
また、個人的に自宅や車などの購入費用として充てた場合は、適正利率で算定した利息相当額を、返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入するが、2013年分のその適正利率は0.7%となる。
この定期借地権の設定に伴い貸主が預かった保証金を個人的に使ってしまった場合などは、貸主に経済的利益が生じたことから課税対象となる。その際の課税対象額は、税務当局が毎年定める「適正利率」によって計算され、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入する。
国税庁はこのほど、その適正利率が、2013年分は前年分から0.1ポイント低い0.7%と、前年2012年分の0.8%を下回り過去最低を記録したことを明らかにした。この「適正利率」は各年度の10年長期国債の平均利率によることとされ、2013年の10年長期国債の平均利率が0.72%だったことから「0.7%」としたもの。この取扱いは、1993年分の不動産所得の申告から始まっているが、同年分は4%。それからずいぶん低下したものだ。
この結果、保証金を事業用資金や事業用資産の取得資金として使う場合に、各年分の不動産所得の収入金額と必要経費に算入する利息相当額を算出する「適正利率」は、平均的な長期借入利率のほか0.7%としても差し支えない。
また、個人的に自宅や車などの購入費用として充てた場合は、適正利率で算定した利息相当額を、返還するまでの各年分の不動産所得の収入金額に算入するが、2013年分のその適正利率は0.7%となる。
投稿者:
2014.02.19更新
【TAO通信】国の借金、12月末で1017兆円
財務省が公表した2013年12月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は1017兆9459億円にのぼった。昨年9月末からは6兆7673億円増加し、初めて1千兆円の大台を突破した同年6月末以降も借金の膨張が止まらない。
2013年9月末に比べ、国債は約9.5兆円増の約849.1兆円で全体の約83%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.9兆円増の約739.7兆円と過去最高を更新した。
この「国の借金」1017兆9459億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約24倍である。年収500万円のサラリーマンが1億2000万円の借金を抱えている勘定だ。
また、わが国の今年1月1日時点での推計人口1億2722万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、昨年9月末時点の約792万円から約800万円に上昇する。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(補正予算ベース)の公債残高は、2013年12月末実績での約739.7兆円から約751.5兆円程度に膨らむと見込まれる。
なお、2013年度末の国の借金は、12月末実績の約1017.9兆円からさらに約20.8兆円増の1038.7兆円になる見通し。今年から2段階の消費増税が予定されているが、それでも財再再建の道は遠のいている。
2013年9月末に比べ、国債は約9.5兆円増の約849.1兆円で全体の約83%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.9兆円増の約739.7兆円と過去最高を更新した。
この「国の借金」1017兆9459億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約24倍である。年収500万円のサラリーマンが1億2000万円の借金を抱えている勘定だ。
また、わが国の今年1月1日時点での推計人口1億2722万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、昨年9月末時点の約792万円から約800万円に上昇する。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(補正予算ベース)の公債残高は、2013年12月末実績での約739.7兆円から約751.5兆円程度に膨らむと見込まれる。
なお、2013年度末の国の借金は、12月末実績の約1017.9兆円からさらに約20.8兆円増の1038.7兆円になる見通し。今年から2段階の消費増税が予定されているが、それでも財再再建の道は遠のいている。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)