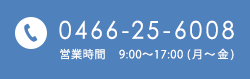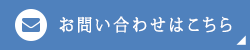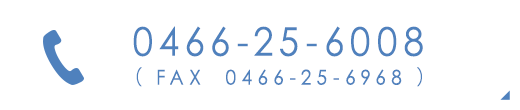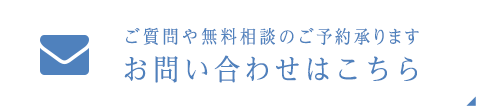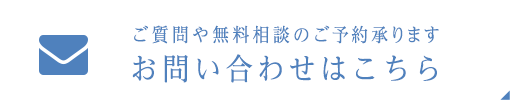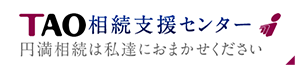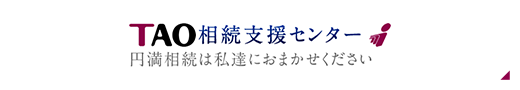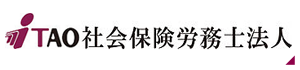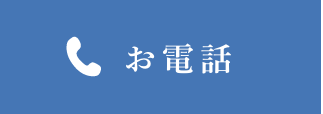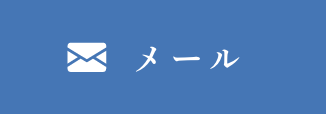国土交通省は、来年4月からの消費税率8%への引上げに伴い、鉄道やバスの運賃支払いにパスモやスイカなどのICカードを利用している場合には、「1円単位運賃」の導入を認めることを明らかにしました。
自動券売機では1円や5円などの少額硬貨の取扱いなどを考慮して、引き続き10円単位の運賃となります。
ICカードの利用割合は、関西圏の約4割に対し首都圏では約8割と高くなっています。これを反映してか、主に首都圏の鉄道事業者、バス事業者の中には1円単位運賃の導入を希望しているところがあります。
1円単位運賃が、消費税率の引上げ分をより正確に転嫁することから運賃改定申請が出た場合の方針を示したもので、原則、ICカード運賃は、現金運賃と同額かそれより安くします。端数処理は、事業全体として108/105以内の増収を前提に、鉄道、バスの利用特性を踏まえて現実的に対応します。
現行150円の鉄道運賃を例にとると、108/105は154円なので、ICカードは154円となります。ICカード運賃は、現金運賃より高くできないので、現金運賃は切上げを認め160円とします。
バスの場合も鉄道運賃と考え方は同じですが、バスは現金利用割合が高い一方、定期券運賃による調整の余地が小さいことから、四捨五入を基本とし、ICカード運賃が現金運賃より高くならないようにします。
2013.11.13更新
【TAO通信】税務調査件数が通則法改正の影響で27%減
国税庁がこのほど公表した今年6月までの1年間(2012事務年度)における法人税調査事績によると、不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万3千法人(前年度比27.4%減)を実地調査した結果、うち約73%にあたる6万8千件(同26.0%減)から前年度に比べ15.0%減の総額9992億円の申告漏れを指摘しました。追徴税額は2098億円(同3.6%減)。1件あたりの申告漏れは同17.2%増の1071万円となります。
実地調査件数は、1月の国税通則法の改正で、課税理由の説明などが原則義務化されて事務作業量が増加した影響から、1件当たりの調査期間が平均2.6日伸びたため大きく減少しました。
また、調査した18.3%(不正発見割合)に当たる1万7千件(前年度比32.1%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比9.6%減の2758億円ですが、1件当たりでは同33.0%増の1613万円と3年ぶりに増加しました。
不正を業種別にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が45.4%で11年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、「パチンコ」(29.8%)、「土木工事」(29.1%)の順で続きます。
一方、1件あたりの不正所得金額が大きい10業種では、1位は「非鉄金属製造」の5626万円、2位は前年まで2年連続トップの「パチンコ」の5037万円、3位は「電気通信機械器具卸売」と続きます。
実地調査件数は、1月の国税通則法の改正で、課税理由の説明などが原則義務化されて事務作業量が増加した影響から、1件当たりの調査期間が平均2.6日伸びたため大きく減少しました。
また、調査した18.3%(不正発見割合)に当たる1万7千件(前年度比32.1%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比9.6%減の2758億円ですが、1件当たりでは同33.0%増の1613万円と3年ぶりに増加しました。
不正を業種別にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が45.4%で11年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、「パチンコ」(29.8%)、「土木工事」(29.1%)の順で続きます。
一方、1件あたりの不正所得金額が大きい10業種では、1位は「非鉄金属製造」の5626万円、2位は前年まで2年連続トップの「パチンコ」の5037万円、3位は「電気通信機械器具卸売」と続きます。
投稿者:
2013.11.06更新
【TAO通信】拡充される所得拡大促進税制に注目
10月1日に公表された民間投資活性化等のための税制改正大綱には、雇用と賃上げの後押しのため、2013年度税制改正で創設されたばかりの所得拡大促進税制が、適用期限が2018年3月末まで2年間延長された上、早くも拡充されることになり、企業の注目を集めている。
現行の同税制は、一定の要件を満たし給与等支給総額を増加させた場合、支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができる制度だ。要件は、(1)基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加、(2)給与等総支給額が前事業年度以上であること、(3)平均給与等総支給額が前事業年度以上であること、の3つ。
今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。
現行の同税制は、一定の要件を満たし給与等支給総額を増加させた場合、支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%、中小企業者等は20%が限度)ができる制度だ。要件は、(1)基準年度と比較して国内雇用者の給与等総支給額が5%以上増加、(2)給与等総支給額が前事業年度以上であること、(3)平均給与等総支給額が前事業年度以上であること、の3つ。
今回の見直しでは、まず(1)の給与等支給増加率が、現行の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和される。また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が現行の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできることになる。
さらに、(3)に関しては、現在は相対的に高賃金の団塊世代の高齢者の退職と低賃金の若年層の採用が平均給与を減少させるため、比較対象を「国内雇用者に対する給与」から「継続雇用者に対する給与」に見直される。つまり、新制度では、退職者や再雇用者、新卒採用者を除いた継続雇用者だけで比較できることになる。
投稿者:
2013.10.30更新
【TAO通信】法人実効税率への企業の意識調査
先日閣議決定された消費増税対応の経済活性化のための税制改正大綱において、法人実効税率の引下げについて「速やかに検討を開始する」ことが明記されましたが、帝国データバンクが実施した「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果(有効回答数1万826社)では、企業の66.6%と3社に2社が法人実効税率を「引き下げるべき」と回答しました。
特に、大企業(64.9%)よりも中小企業(67.0%)で引下げを求める企業が多くなっています。
実効税率引下げ分の使い道は、「内部留保」が22.8%で最多、5社に1社は実効税率の引下げ分を自社内にとどめ置くとのこと。
人的投資に対しては、「社員に還元(給与や賞与の増額など)」(16.1%)や「人員の増強」(12.4%)が計28.5%と3割近く、また、「設備投資の増強」(16.2%)や「研究投資の拡大」(4.8%)など資本投資が計21.0%となっており、人的投資と資本投資を合わせ49.5%と、ほぼ半数の企業が積極的な投資に使うことを想定しています。
企業規模別にみると、人的投資は、「大企業」(26.8%)より「中小企業」(29.0%)が2.2ポイント多く、「中小企業」ほど社員への還元や人員拡大など人的投資に振り分ける傾向があります。しかし、「借入金の返済」(全体では14.5%)では、「中小企業」(15.3%)のほうが「大企業」(11.9%)を3.4ポイント上回っており、実効税率引下げ分の使い道として債務の削減を図る傾向が強くなっています。
特に、大企業(64.9%)よりも中小企業(67.0%)で引下げを求める企業が多くなっています。
実効税率引下げ分の使い道は、「内部留保」が22.8%で最多、5社に1社は実効税率の引下げ分を自社内にとどめ置くとのこと。
人的投資に対しては、「社員に還元(給与や賞与の増額など)」(16.1%)や「人員の増強」(12.4%)が計28.5%と3割近く、また、「設備投資の増強」(16.2%)や「研究投資の拡大」(4.8%)など資本投資が計21.0%となっており、人的投資と資本投資を合わせ49.5%と、ほぼ半数の企業が積極的な投資に使うことを想定しています。
企業規模別にみると、人的投資は、「大企業」(26.8%)より「中小企業」(29.0%)が2.2ポイント多く、「中小企業」ほど社員への還元や人員拡大など人的投資に振り分ける傾向があります。しかし、「借入金の返済」(全体では14.5%)では、「中小企業」(15.3%)のほうが「大企業」(11.9%)を3.4ポイント上回っており、実効税率引下げ分の使い道として債務の削減を図る傾向が強くなっています。
投稿者:
2013.10.23更新
【TAO通信】12年度法人黒字申告割合は27.4%
国税庁がこのほど発表した2012年度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度から0.3%増の298万5千法人で、うち今年7月までに申告したのは、同0.1%減の276万1千法人。
その申告所得金額は同21.2%(7兆8991億円)増の45兆1874億円、申告税額の総額も同5.0%(4753億円)増の10兆105億円と、ともに3年連続の増加となりました。申告所得の増加率が20%を超えたのは25年ぶり。
この結果、法人の黒字申告割合は前年度に比べ1.5ポイント上昇して27.4%となり、2年連続の増加となりました。もっとも、過去最低だった2010年度(25.2%)までは、初めて30%を割り込んだ2008年度から3年連続で過去最低を更新していたもので、黒字申告割合は低水準が続いています。法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から20年も続いていることになります。
3年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて14.5%増の5966万円となりました。一方、申告欠損金額は、同22.6%減の16兆8226億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同20.9%減の840万円と、ともに大幅に減少し、企業業績の改善がうかがえる結果となりました。ちなみに、申告所得金額のピークは2006年度の57兆828億円、申告欠損金額のピークは2002年度の1999年度の33兆2791億円です。
その申告所得金額は同21.2%(7兆8991億円)増の45兆1874億円、申告税額の総額も同5.0%(4753億円)増の10兆105億円と、ともに3年連続の増加となりました。申告所得の増加率が20%を超えたのは25年ぶり。
この結果、法人の黒字申告割合は前年度に比べ1.5ポイント上昇して27.4%となり、2年連続の増加となりました。もっとも、過去最低だった2010年度(25.2%)までは、初めて30%を割り込んだ2008年度から3年連続で過去最低を更新していたもので、黒字申告割合は低水準が続いています。法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から20年も続いていることになります。
3年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて14.5%増の5966万円となりました。一方、申告欠損金額は、同22.6%減の16兆8226億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同20.9%減の840万円と、ともに大幅に減少し、企業業績の改善がうかがえる結果となりました。ちなみに、申告所得金額のピークは2006年度の57兆828億円、申告欠損金額のピークは2002年度の1999年度の33兆2791億円です。
投稿者:
2013.10.17更新
【TAO通信】印紙税減税で税務調査が厳しくなる?
2013年度税制改正での印紙税減税を受けて、印紙税の調査が厳しくなるものと思われます。領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が、現行の「記載金額3万円未満」から2014年4月1日以降に作成される受取書からは「5万円未満」に引き上げられるほか、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が拡充されます。
来年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられ、1千万円以下の契約書についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されます。
改正が行われた部分については税務調査でのチェックも厳しくなる傾向があるので要注意です。
調査官は、記載金額が3万円以上なのに収入印紙が貼っていない領収書を見つけると、白紙の領収書なら架空取引を疑い、記載金額の支払い方法や、払出口座などを確認。またボールペンの色が一部変わっていたり、異なる筆跡が混ざったりしたら、経費の水増しを疑われます。数字の頭に1を足したり、1を4に書き換えるなどはよくある手口で、インクの色や筆跡、筆圧などの違いから見抜くこともできるそう。
印紙税を貼っていないことによるペナルティは納付しなかった税額の3倍。消印していない場合は、その収入印紙の額面と同額の過怠税が徴収されます。印紙税は会社の必要経費になりますが、過怠税は必要経費にできません。印紙税の取扱いには十分な注意が必要となります。
来年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられ、1千万円以下の契約書についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されます。
改正が行われた部分については税務調査でのチェックも厳しくなる傾向があるので要注意です。
調査官は、記載金額が3万円以上なのに収入印紙が貼っていない領収書を見つけると、白紙の領収書なら架空取引を疑い、記載金額の支払い方法や、払出口座などを確認。またボールペンの色が一部変わっていたり、異なる筆跡が混ざったりしたら、経費の水増しを疑われます。数字の頭に1を足したり、1を4に書き換えるなどはよくある手口で、インクの色や筆跡、筆圧などの違いから見抜くこともできるそう。
印紙税を貼っていないことによるペナルティは納付しなかった税額の3倍。消印していない場合は、その収入印紙の額面と同額の過怠税が徴収されます。印紙税は会社の必要経費になりますが、過怠税は必要経費にできません。印紙税の取扱いには十分な注意が必要となります。
投稿者:
2013.10.10更新
【TAO通信】来年4月に消費税8%引上げ決定
政府は10月1日の閣議において、来年4月の消費税率8%への引上げを決定するとともに、消費増税による景気への影響を緩和するため、約1兆円規模の減税となる民間投資活性化等のための税制改正大綱を発表しました
注目されていた復興特別法人税の1年前倒し廃止は12月中に結論を得る方針のほか、消費増税に伴う低所得者向けの現金給付や住宅購入者向けの現金給付は、5兆円規模の経済対策の中で手当てされます。
約1兆円規模の前倒しの税制改正は、(1)企業が2015年度末までに、先端設備等を導入した場合、即時償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進税制の創設、(2)企業が給与総額を2%(現行5%)増やした場合、増加分の10%を税額控除する所得拡大促進税制の要件緩和、(3)中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への投資時に税額控除する対象企業を、資本金3千万円以下から1億円以下に拡大する、(4)研究開発税制について、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、控除率を5%から最大30%に引き上げる、などが盛り込まれています。
投資促進税制は、控除率は2015年度末までは5%だが、それ以降2016年度末までは4%となり、企業に早期の投資を促します。所得拡大促進税制も、適用条件を、2013~14年度は「2%以上」、2015年度は「3%以上」、2017年度までは「5%以上」とするなど、早期の適用が有利となります。
注目されていた復興特別法人税の1年前倒し廃止は12月中に結論を得る方針のほか、消費増税に伴う低所得者向けの現金給付や住宅購入者向けの現金給付は、5兆円規模の経済対策の中で手当てされます。
約1兆円規模の前倒しの税制改正は、(1)企業が2015年度末までに、先端設備等を導入した場合、即時償却か5%の税額控除を認める生産性向上設備投資促進税制の創設、(2)企業が給与総額を2%(現行5%)増やした場合、増加分の10%を税額控除する所得拡大促進税制の要件緩和、(3)中小企業投資促進税制について、160万円以上の機械への投資時に税額控除する対象企業を、資本金3千万円以下から1億円以下に拡大する、(4)研究開発税制について、研究開発費の増加分に応じた税額控除で、控除率を5%から最大30%に引き上げる、などが盛り込まれています。
投資促進税制は、控除率は2015年度末までは5%だが、それ以降2016年度末までは4%となり、企業に早期の投資を促します。所得拡大促進税制も、適用条件を、2013~14年度は「2%以上」、2015年度は「3%以上」、2017年度までは「5%以上」とするなど、早期の適用が有利となります。
投稿者:
2013.10.02更新
【TAO通信】ビッグデータ効果、年7兆7700億円
最近「ビッグデータ」という言葉をよく耳にするが、企業経営にどんな効果をもたらすのか、9月公表の2013年版の情報通信白書(総務省)にその答えがあった。
経済効果は、個人の購買履歴などの膨大な情報(ビッグデータ)をフル活用した場合、年間7兆7700億円が見込めると試算した。この数字は小売業、製造業、農業、インフラの4分野の合計額で、販売拡大やコスト削減、渋滞解消などにつながるというのだから「ビッグ」だ。
小売業では、購買履歴の分析で販売促進や発注の最適化が可能になり、1兆1500億円の経済効果を見込む。4千億円の効果を見込む農業では、栽培や土壌データ分析で最適な肥料や農薬量を機械的に計算できるようになると予想。
インフラ関連では、カーナビなどのデータを活用することで渋滞減少が燃費向上に寄与し1兆4300億円の効果を見込む。製造業では業務用機械の故障の減少などにより、4兆7900億円の経済効果があると試算した。
この他、カード不正利用検知、スポーツ選手活用事例など分析競争優位を獲得している企業の導入事例は多い。医薬品開発に役立てたい製薬会社は、個人情報の問題はあるが、調剤薬局の患者情報に関心を寄せている。
ビッグデータ分析は、企業などが売れ筋分析や新製品開発に役立てる有力な経営手段として積極的な活用がさらに進むだろう。
経済効果は、個人の購買履歴などの膨大な情報(ビッグデータ)をフル活用した場合、年間7兆7700億円が見込めると試算した。この数字は小売業、製造業、農業、インフラの4分野の合計額で、販売拡大やコスト削減、渋滞解消などにつながるというのだから「ビッグ」だ。
小売業では、購買履歴の分析で販売促進や発注の最適化が可能になり、1兆1500億円の経済効果を見込む。4千億円の効果を見込む農業では、栽培や土壌データ分析で最適な肥料や農薬量を機械的に計算できるようになると予想。
インフラ関連では、カーナビなどのデータを活用することで渋滞減少が燃費向上に寄与し1兆4300億円の効果を見込む。製造業では業務用機械の故障の減少などにより、4兆7900億円の経済効果があると試算した。
この他、カード不正利用検知、スポーツ選手活用事例など分析競争優位を獲得している企業の導入事例は多い。医薬品開発に役立てたい製薬会社は、個人情報の問題はあるが、調剤薬局の患者情報に関心を寄せている。
ビッグデータ分析は、企業などが売れ筋分析や新製品開発に役立てる有力な経営手段として積極的な活用がさらに進むだろう。
投稿者:
2013.09.25更新
【TAO通信】消費税率引上げに対する企業意識
帝国データバンクが8月下旬に実施した「消費税率引上げに対する企業の意識調査」結果(有効回答数1万1114社)によると、消費税率引上げの自社の業績への影響は、「悪影響」と回答した企業が47.7%で最多、「かなり悪影響」(7.7%)を合わせると、業績に悪影響があると考える企業は55.3%と半数超にのぼりました。
他方、「影響はない」は25.3%である一方、「好影響」(1.9%)と「かなり好影響」(0.4%)はわずか2.4%にとどまっています。
「悪影響」計を業界別にみると、「小売」が80.5%と最も高く、「農・林・水産」(73.3%)も7割を超える高水準。消費者に最も近い業界である「小売」と、食料品の生産を担う「農・林・水産」で業績への影響を懸念する企業の割合が突出しています。前回2012年7月調査と比べると、「好影響」計がほぼ同水準(前回2.0%)だったのに対し、景気の上昇傾向を通じて業績への懸念がやや薄まったこともあり、「悪影響」計は11.8ポイント減少しました。
消費税率引上げを理由とした納入価格引下げ要請があった場合の対応では、「条件や企業との関係性による」との回答が46.0%で最多。また、「承諾しない」は33.1%と3社に1社にとどまりました。他方、「承諾する」は5.9%と1割未満ながら、一定数の企業が要請に応じると考えていることが分かりました。
規模別にみると、「大企業」が5.4%、「中小企業」6.1%、「小規模企業」7.4%と、規模が小さくなるにつれ要請に応じる傾向があります。
他方、「影響はない」は25.3%である一方、「好影響」(1.9%)と「かなり好影響」(0.4%)はわずか2.4%にとどまっています。
「悪影響」計を業界別にみると、「小売」が80.5%と最も高く、「農・林・水産」(73.3%)も7割を超える高水準。消費者に最も近い業界である「小売」と、食料品の生産を担う「農・林・水産」で業績への影響を懸念する企業の割合が突出しています。前回2012年7月調査と比べると、「好影響」計がほぼ同水準(前回2.0%)だったのに対し、景気の上昇傾向を通じて業績への懸念がやや薄まったこともあり、「悪影響」計は11.8ポイント減少しました。
消費税率引上げを理由とした納入価格引下げ要請があった場合の対応では、「条件や企業との関係性による」との回答が46.0%で最多。また、「承諾しない」は33.1%と3社に1社にとどまりました。他方、「承諾する」は5.9%と1割未満ながら、一定数の企業が要請に応じると考えていることが分かりました。
規模別にみると、「大企業」が5.4%、「中小企業」6.1%、「小規模企業」7.4%と、規模が小さくなるにつれ要請に応じる傾向があります。
投稿者:
2013.09.18更新
【TAO通信】有識者の7割超が増税に賛成表明
安倍晋三首相が消費税引上げを最終判断する時期が近付いていますが、内閣府は、8月26日から31日の間に7回にわたって開かれた、消費税増税の影響を検証した集中点検会合の概要報告を公表しました。
会合では60名の有識者からヒアリングを行った結果、7割超の44名が予定通り消費税率を引上げに賛成意見を表明しました。
その理由として、財政健全化が急務であること、社会保障の充実とそのための財源を確保すること、将来世代への負担の先送りをやめて世代間格差の是正を図ること、地方においても財源確保の必要性が高いこと、国際社会や市場からの信認の保持などが挙げられました。
また、経済・金融の専門家からは、前回5%に引上げ時の1997年の景気後退の主因は消費税率引上げとは言えず、予定通り実施しない理由にはならないとの指摘がありました。
一方で、1割超の有識者からは、デフレ脱却を確実なものとするなどのため、予定を変更して毎年1%ずつ、5年間で合計5%引き上げる案や引上げを1年先送る案などが提示されました。
こうした意見に対しては、デフレ脱却まで消費税率引上げを待つと金融・財政同時引締めのリスクが高いとの意見や、すでに民間企業や市場は引上げを織り込んでおり、予定変更が経済活動の混乱を招くことや、小刻みな引上げは、実務上のコスト増が懸念されること、円滑な転嫁を懸念する意見などが、中小企業団体の代表者など経済界を中心に出されました。
会合では60名の有識者からヒアリングを行った結果、7割超の44名が予定通り消費税率を引上げに賛成意見を表明しました。
その理由として、財政健全化が急務であること、社会保障の充実とそのための財源を確保すること、将来世代への負担の先送りをやめて世代間格差の是正を図ること、地方においても財源確保の必要性が高いこと、国際社会や市場からの信認の保持などが挙げられました。
また、経済・金融の専門家からは、前回5%に引上げ時の1997年の景気後退の主因は消費税率引上げとは言えず、予定通り実施しない理由にはならないとの指摘がありました。
一方で、1割超の有識者からは、デフレ脱却を確実なものとするなどのため、予定を変更して毎年1%ずつ、5年間で合計5%引き上げる案や引上げを1年先送る案などが提示されました。
こうした意見に対しては、デフレ脱却まで消費税率引上げを待つと金融・財政同時引締めのリスクが高いとの意見や、すでに民間企業や市場は引上げを織り込んでおり、予定変更が経済活動の混乱を招くことや、小刻みな引上げは、実務上のコスト増が懸念されること、円滑な転嫁を懸念する意見などが、中小企業団体の代表者など経済界を中心に出されました。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)