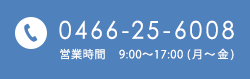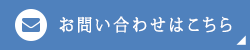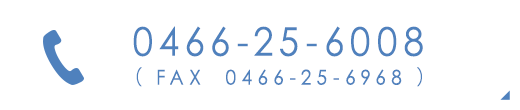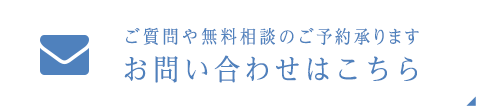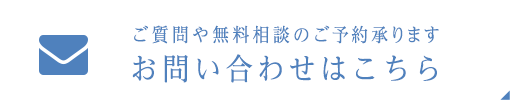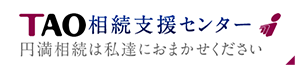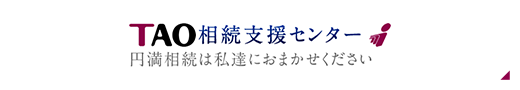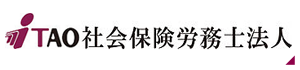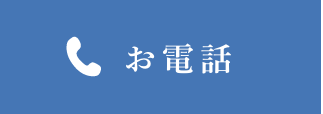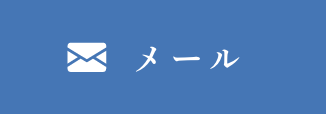「ふるさと納税」は、自分が住んでいる住所地以外の地方自治体に税を寄附(納税)して特産品を受け取り、しかも確定申告すれば、所得税や住民税の税額控除を受けられる。
年々、人気が高まるなか、総務省は税制改正で制度を拡充する方針を固めた。政府は地方活性化に本腰を入れるため、新たに「まち・ひと・しごと創生対策本部」を設置し、ふるさと納税もその起爆剤のひとつにしたい考えだ。
ふるさと納税は、寄附金のうち2000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みだ。住民税の控除の上限は所得割額の1割。例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し3万円の寄付をした場合、控除額は2万8000円となる。
総務省はこの控除制度を簡易化することや限度額を2割に引き上げる方向で検討している。
上記の年収700万円の夫婦子なし世帯の場合、現在、寄附金控除対象の寄附の上限は5万5000円で、ここから2000円の自己負担分を引いた全額が軽減されるが、上限が2倍に引き上げられると、単純計算で11万円までが寄附金控除の対象になり、控除額は最大で10万8000円になる。また、寄附を受けた自治体から寄附者が住む市区町村へ情報を伝えることで、寄附者が役所に行かなくても控除を受けられる仕組みが検討されるという。
2014.08.27更新
【TAO通信】2013年度租税滞納状況
国税庁が先日公表した2013年度租税滞納状況によると、新規発生滞納の抑制及び滞納整理の促進により、今年3月末時点の滞納残高は15年連続して減少、ピークの1998年度の約41%まで低下している。
同庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいる。
原告訴訟に関しては、2013年度は146件(前年度155件)の訴訟を提起した。訴訟の内訳は、「差押債権取立」12件(同25件)、「供託金取立等」7件(同15件)、「その他(債権届出など)」120件(同108件)のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が7件(同7件)となった。
そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴が33件、一部・全部敗訴が4件などだった。
また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処している。同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科とされている。2013年度は、1年間の告発件数では昨年に引き続き過去最多となる6事案を同罪で告発している。
同庁では、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となる訴訟を提起したり、滞納処分免脱罪による告発を活用して、積極的に滞納整理に取り組んでいる。
原告訴訟に関しては、2013年度は146件(前年度155件)の訴訟を提起した。訴訟の内訳は、「差押債権取立」12件(同25件)、「供託金取立等」7件(同15件)、「その他(債権届出など)」120件(同108件)のほか、特に悪質な事案で用いられる「名義変更・詐害行為」が7件(同7件)となった。
そして、係属事件を含め154件が終結し、国側勝訴が33件、一部・全部敗訴が4件などだった。
また、財産の隠ぺいなどにより滞納処分の執行を免れようとする悪質な滞納者に対しては、「滞納処分免脱罪」の告発を行うなど、特に厳正に対処している。同免脱罪の罰則は、3年以下の懲役か250万円以下の罰金に処し、またはこれを併科とされている。2013年度は、1年間の告発件数では昨年に引き続き過去最多となる6事案を同罪で告発している。
投稿者:
2014.08.20更新
【TAO通信】復興特別所得税の記載漏れに注意
復興特別法人税は2014年度税制改正において1年前倒しで廃止されたが、復興特別所得税は昨年1月から2037年12月31日まで25年間にわたって課税される。国税庁では、その最初の適用となった2013年分確定申告において、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されている。
復興特別所得税は、2011年12月に施行された復興財源確保法で創設され、2013年分から2037年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額を、所得税とともに申告・納付することになっている。国税当局は、2013年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行っていた。しかし、先の2013年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を"空欄"のまま提出していた納税者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%を占めたという。このため国税庁では、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うこととした。今後24年間を残す課税期間を考えれば、周知・指導は不可欠といえよう。なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなるが、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加される。
復興特別所得税は、2011年12月に施行された復興財源確保法で創設され、2013年分から2037年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額を、所得税とともに申告・納付することになっている。国税当局は、2013年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行っていた。しかし、先の2013年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を"空欄"のまま提出していた納税者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%を占めたという。このため国税庁では、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うこととした。今後24年間を残す課税期間を考えれば、周知・指導は不可欠といえよう。なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなるが、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加される。
投稿者:
2014.08.13更新
【TAO通信】国税の滞納残高は15年連続で減少
今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ10.1%減の1兆1414億円となり、1999年度以降15年連続で減少したことが、国税庁が発表した2013年度租税滞納状況で明らかになった。新規発生滞納額は前年度に比べ7.7%減の5477億円と5年連続で減少し、整理済額は同1.3%減の6765億円と減少したものの、整理済額が新規発生滞納額を大きく上回ったため、滞納残高も減少した。
今年3月までの1年間(2013年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約29%まで減少した。また、2013年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.1%と前年度を0.2ポイント下回った。2004年度以降、10年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっている。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約41%まで減少した。
税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比11.5%減の2814億円と5年連続で減少したが、税目別では9年連続で最多、全体の約51%を占める。一方で、整理済額が3210億円と上回ったため、滞納残高は10.0%減の3564億円と、14年連続で減少した。法人税も、新規発生滞納額は同0.7%増の691億円と5年ぶりに増加したが、整理済額が907億円と上回ったため、滞納残高も13.2%減の1419億円と6年連続で減少した。
今年3月までの1年間(2013年度)に発生した新規滞納額は、最も新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8903億円)の約29%まで減少した。また、2013年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は1.1%と前年度を0.2ポイント下回った。2004年度以降、10年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっている。この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8149億円)の約41%まで減少した。
税目別にみると、消費税は、新規発生滞納額が前年度比11.5%減の2814億円と5年連続で減少したが、税目別では9年連続で最多、全体の約51%を占める。一方で、整理済額が3210億円と上回ったため、滞納残高は10.0%減の3564億円と、14年連続で減少した。法人税も、新規発生滞納額は同0.7%増の691億円と5年ぶりに増加したが、整理済額が907億円と上回ったため、滞納残高も13.2%減の1419億円と6年連続で減少した。
投稿者:
2014.08.06更新
【TAO通信】国税職員の異動期の税務調査に異変
これまでの税務調査の通説として、7月は全国の国税職員の人事異動があり、8月は調査先がお盆休みの時期に入るということで、「真夏に税務調査はしない」といわれてきた。7月は国税当局の事務年度初めということもあり、税務調査は6月末までに一応の区切りをつけておき、7〜8月は前事務年度からの持越し事案か、秋の本格的な調査シーズンに備えた机上調査に力を入れる期間、とされていた。
ところが、数年前から少し状況が変わってきているという。「異動時期に調査の空白期間が生じないよう、内示日から動くように変えた」と語るのは、地方国税局の幹部経験もある国税OB税理士だ。
国税職員の人事異動の発令日は7月10日だが、その1週間前に内示がある。内示段階で自分が動くか分かるため、残留となった調査官は、その日の午後には選定済みの調査先に事前通知を発送。早々に調査を実施、お盆休み前に何件か片付けるのだ。残留組がこの時期しっかり動くことで、調査の空白期間がなくなり件数が稼げる、という。通則法改正による調査手続きの見直し等で調査件数が激減しているなか、1件でも数をこなしたい国税当局にとってこの"奇策"は無理なくハマり、今は全国に広がっているという。「真夏に税務調査はしない」というのは今や昔。調査件数が減少傾向にあるなか、国税当局はこれまで以上に念を入れた準備調査に加え、実地調査もお盆前に数件はこなしている。世の社長たちも税理士も、認識を改めておく必要がある。
ところが、数年前から少し状況が変わってきているという。「異動時期に調査の空白期間が生じないよう、内示日から動くように変えた」と語るのは、地方国税局の幹部経験もある国税OB税理士だ。
国税職員の人事異動の発令日は7月10日だが、その1週間前に内示がある。内示段階で自分が動くか分かるため、残留となった調査官は、その日の午後には選定済みの調査先に事前通知を発送。早々に調査を実施、お盆休み前に何件か片付けるのだ。残留組がこの時期しっかり動くことで、調査の空白期間がなくなり件数が稼げる、という。通則法改正による調査手続きの見直し等で調査件数が激減しているなか、1件でも数をこなしたい国税当局にとってこの"奇策"は無理なくハマり、今は全国に広がっているという。「真夏に税務調査はしない」というのは今や昔。調査件数が減少傾向にあるなか、国税当局はこれまで以上に念を入れた準備調査に加え、実地調査もお盆前に数件はこなしている。世の社長たちも税理士も、認識を改めておく必要がある。
投稿者:
2014.07.30更新
【TAO通信】3割を下回る贈与税改正の認知度
来年1月から相続税は基礎控除が大きく引き下げられるなど課税が強化される一方、贈与税は、20歳以上の者が父母や祖父母など直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税率が引き下げられるなど課税が緩和される。
信託協会が、40歳以上の子供がいる既婚者を対象に5月に実施した「相続に関する意識調査」結果(有効回答数3927人)によると、相続財産を「受け取る可能性がある」人は全体の45.2%と半数に近くを占めた。ただし、「受け取る可能性がある」人で、対策を「してもらっている」人は19.9%と2割にとどまる。具体的な相続対策は、「生前における定期的・計画的な贈与」が62.4%、「生命保険の活用」(25.7%)、「遺言書の作成」(25.5%)などが続いた。相続対策をしてもらっている人は2割にとどまるが、「受け取る可能性がある」人の50.9%は「相続対策の必要性を感じている」と回答。必要な対策として43.3%が「遺言書の作成」を挙げ、具体的な対策として挙げていた「遺言書の作成」(25.5%)と比べて割合が高い。
2015年1月から課税強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%と約5割だったのに対し、課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%と3割を下回った。他方、昨年4月から開始(2015年12月31日までの3年間の措置)されている「教育資金贈与税非課税制度」については、「知っていた」との回答が56.3%と最も多かった。
信託協会が、40歳以上の子供がいる既婚者を対象に5月に実施した「相続に関する意識調査」結果(有効回答数3927人)によると、相続財産を「受け取る可能性がある」人は全体の45.2%と半数に近くを占めた。ただし、「受け取る可能性がある」人で、対策を「してもらっている」人は19.9%と2割にとどまる。具体的な相続対策は、「生前における定期的・計画的な贈与」が62.4%、「生命保険の活用」(25.7%)、「遺言書の作成」(25.5%)などが続いた。相続対策をしてもらっている人は2割にとどまるが、「受け取る可能性がある」人の50.9%は「相続対策の必要性を感じている」と回答。必要な対策として43.3%が「遺言書の作成」を挙げ、具体的な対策として挙げていた「遺言書の作成」(25.5%)と比べて割合が高い。
2015年1月から課税強化される「相続税改正」を「知っている」との回答は50.9%と約5割だったのに対し、課税が緩和される「贈与税改正」の認知度は27.3%と3割を下回った。他方、昨年4月から開始(2015年12月31日までの3年間の措置)されている「教育資金贈与税非課税制度」については、「知っていた」との回答が56.3%と最も多かった。
投稿者:
2014.07.25更新
【TAO通信】交際費50%損金算入の適用時期に注意
2014年度税制改正では、法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2015年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されている接待飲食費の額の50%を損金に算入できる制度が盛り込まれた。
同制度においては、中小法人に限らず、これまで支出する交際費等の全額が損金不算入とされていた大法人も適用できることから、接待飲食の場が拡がると見込まれている。
しかし、経理担当者として気を付けたいのが、その適用関係である。同制度の適用時期は、法人の2014年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されることから、結果として、その事業年度が開始している法人の支出する接待飲食費が対象となる。
したがって、その法人の事業年度等をベースとした適用関係であり、接待飲食費の支出ベースでの適用関係とはならないことから、今年4月1日以後に支出をした接待飲食費であっても、その支出をした日の属する事業年度等が今年4月1日前に開始した事業年度である法人の場合には適用されず、交際費等の範囲から除外することはできないことになる。特に新たに適用される大法人の経理担当者は注意したいところだ。
同制度においては、中小法人に限らず、これまで支出する交際費等の全額が損金不算入とされていた大法人も適用できることから、接待飲食の場が拡がると見込まれている。
しかし、経理担当者として気を付けたいのが、その適用関係である。同制度の適用時期は、法人の2014年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されることから、結果として、その事業年度が開始している法人の支出する接待飲食費が対象となる。
したがって、その法人の事業年度等をベースとした適用関係であり、接待飲食費の支出ベースでの適用関係とはならないことから、今年4月1日以後に支出をした接待飲食費であっても、その支出をした日の属する事業年度等が今年4月1日前に開始した事業年度である法人の場合には適用されず、交際費等の範囲から除外することはできないことになる。特に新たに適用される大法人の経理担当者は注意したいところだ。
投稿者:
2014.07.18更新
【TAO通信】小規模企業の消費増税分の転嫁困難
全国商工会連合会が実施した「中小・小規模企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査」結果(有効回答数3626社)によると、消費税8%への引上げが行われた4月以降、全体の4割超の中小・小規模企業が消費税引上げ分を「転嫁できていない」(「全く転嫁できていない(10.5%)」、「一部転嫁できていない(30.6%)」)と回答した。
特に、個人事業主や資本金規模の小さな事業者は転嫁できない割合が高い。
「転嫁できていない」との回答を業種別にみると、「飲食業」(51.6%)や「不動産業」(50.0%)、「宿泊業」(45.4%)、「小売業」(43.7%)など、主に消費者を相手に事業を営んでいる業種において割合が高い。転嫁できている理由としては、「商品・サービスの特性」が3割前後を占めている。
一方、転嫁できていない理由としては、「消費者の低価格ニーズへの対応」や「競合相手との競争が激しい」が目立つ。
また、消費税10%への引上げを想定した今後の転嫁状況の見通しについても、課税売上高1000万円以下の小規模企業では、「今後も転嫁できない」(11.5%)及び「転嫁できるかどうかわからない」(37.3%)で約5割を占め、売上規模の小さな事業ほど転嫁見込みは不透明となっている。
10%への引上げ判断に当たっては、今回の税率引上げの影響が一時的なもので終息するのか否か、慎重に見極める必要があると指摘している。
特に、個人事業主や資本金規模の小さな事業者は転嫁できない割合が高い。
「転嫁できていない」との回答を業種別にみると、「飲食業」(51.6%)や「不動産業」(50.0%)、「宿泊業」(45.4%)、「小売業」(43.7%)など、主に消費者を相手に事業を営んでいる業種において割合が高い。転嫁できている理由としては、「商品・サービスの特性」が3割前後を占めている。
一方、転嫁できていない理由としては、「消費者の低価格ニーズへの対応」や「競合相手との競争が激しい」が目立つ。
また、消費税10%への引上げを想定した今後の転嫁状況の見通しについても、課税売上高1000万円以下の小規模企業では、「今後も転嫁できない」(11.5%)及び「転嫁できるかどうかわからない」(37.3%)で約5割を占め、売上規模の小さな事業ほど転嫁見込みは不透明となっている。
10%への引上げ判断に当たっては、今回の税率引上げの影響が一時的なもので終息するのか否か、慎重に見極める必要があると指摘している。
投稿者:
2014.07.09更新
【TAO通信】2014年分路線価、平均▲0.7%下落
全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2014年分の路線価及び評価倍率が公表された。今年1月1日時点の全国約33万96千地点(継続地点)における標準宅地の前年比の変動率の平均は▲0.7%下落し、6年連続の下落となった。
しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1%→2.8%→1.8%→0.7%と着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。
都道府県別の路線価をみると、昨年分で上昇に転じた宮城・愛知の2県に加え、福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪の1都1府・6県に増え、沖縄県も横ばいまで回復している。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の41道府県から38道府県に減少したが、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年の4県から今年分はゼロとなった。ちなみに、東京は+1.8%(前年分▲0.3%)、大阪は+0.3%(同▲0.8%)。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の7都市から18都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ8都市、最高路線価が下落した都市は昨年の32都市から21都市に減少した。
このうち上昇率「5%以上」の都市は、昨年の3都市から8都市に、また、上昇率「5%未満」の都市は、昨年の4都市から10都市へと大幅に増えており、地価の上昇傾向が地方の中心都市にも広がりつつある。
しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1%→2.8%→1.8%→0.7%と着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。
都道府県別の路線価をみると、昨年分で上昇に転じた宮城・愛知の2県に加え、福島・埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪の1都1府・6県に増え、沖縄県も横ばいまで回復している。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の41道府県から38道府県に減少したが、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年の4県から今年分はゼロとなった。ちなみに、東京は+1.8%(前年分▲0.3%)、大阪は+0.3%(同▲0.8%)。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の7都市から18都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ8都市、最高路線価が下落した都市は昨年の32都市から21都市に減少した。
このうち上昇率「5%以上」の都市は、昨年の3都市から8都市に、また、上昇率「5%未満」の都市は、昨年の4都市から10都市へと大幅に増えており、地価の上昇傾向が地方の中心都市にも広がりつつある。
投稿者:
2014.07.02更新
【TAO通信】2013年度査察の脱税総額は145億円
いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。国税庁が公表した2013年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より5件少ない185件、脱税総額は前年度を29.4%下回る約145億円と1974年度(約123億円)以来39年ぶりの低水準だった。これは、脱税額3億円以上の大口事案が前年度を7件下回る4件と大幅に減少したことなどが要因。
今年3月までの1年間(2013年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は185件と、42年ぶりの低水準だった前年度をさらに5件下回った。継続事案を含む185件(前年度191件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち63.8%(同67.5%)に当たる118件(同129件)を検察庁に告発した。この告発率63.8%は、前年度から3.7ポイント減少し、38年ぶりの低水準だった2011年度(61.9%)に次ぐ低い割合だった。
告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは4件にとどまり、脱税額が5億円以上は同1件少ない2件だった。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2013年度の脱税総額145億円は、ピークの1988年度(714億円)の約20%にまで減少している。告発分の脱税総額は前年度を約58億円下回る約117億円、1件当たり平均の脱税額は同3600万円減の9900万円と、1978年度(9500万円)以来35年ぶりに1億円を下回った。
今年3月までの1年間(2013年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は185件と、42年ぶりの低水準だった前年度をさらに5件下回った。継続事案を含む185件(前年度191件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち63.8%(同67.5%)に当たる118件(同129件)を検察庁に告発した。この告発率63.8%は、前年度から3.7ポイント減少し、38年ぶりの低水準だった2011年度(61.9%)に次ぐ低い割合だった。
告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは4件にとどまり、脱税額が5億円以上は同1件少ない2件だった。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2013年度の脱税総額145億円は、ピークの1988年度(714億円)の約20%にまで減少している。告発分の脱税総額は前年度を約58億円下回る約117億円、1件当たり平均の脱税額は同3600万円減の9900万円と、1978年度(9500万円)以来35年ぶりに1億円を下回った。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)