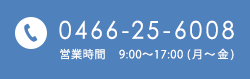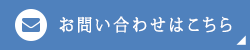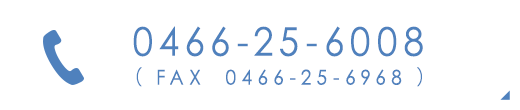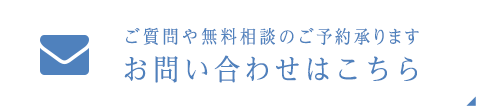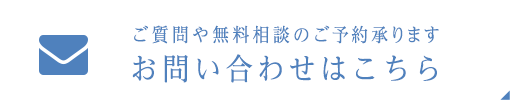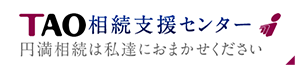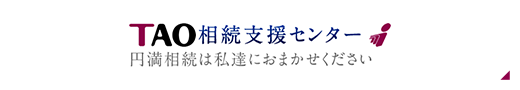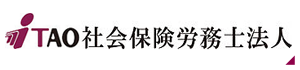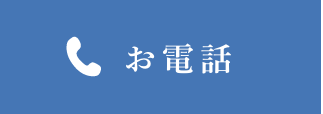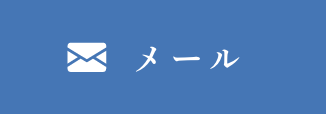国税庁がこのほど公表した2014年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より9件多い194件、脱税総額は39年ぶりの低水準だった前年度を3.6%上回る約145億円となった。
今年3月までの1年間(2014年度)に、全国の国税局が査察に着手した件数は194件と、前年度を9件上回った。継続事案を含む180件(前年度185件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち62.2%(同63.8%)に当たる112件(同118件)を検察庁に告発した。この告発率62.2%は、前年度から1.6ポイント減少し、38年ぶりの低水準だった2011年度(61.9%)に次ぐ低い割合だった。
告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは前年度より2件多い6件にとどまった。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、2014年度の脱税総額150億円は、ピークの1988年度(714億円)の約21%にまで減少している。告発分の脱税総額は前年度を約6億円上回る約123億円、1件当たり平均の脱税額は1億1000万円と、35年ぶりに1億円を下回った前年度を1100万円上回った。
告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、「不動産業」が16件でトップ、次いで「クラブ・バー」が10件、「建設業」が8件、「運送業」と「広告業」が各4件で続く。「不動産業」では、売上除外や核の経費を計上していたもの、「クラブ・バー」では、ホステス報酬に係る源泉所得税を徴収していながら未納付だったものが多い。
2015.07.08更新
【TAO通信】2015年分路線価は7年連続下落
全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2015年分の路線価及び評価倍率が公表された。
今年1月1日時点の全国約32万9千地点(継続地点)における標準宅地の前年比の変動率の平均は▲0.4%下落し、7年連続の下落となった。しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1%→2.8%→1.8%→0.7%→0.4%と、5年連続で着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。
都道府県別の路線価をみると、標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値の上昇率が「5%未満」の都道府県は、昨年分の1都1府・6県から1都2府7県に増え、滋賀県、福岡県も横ばいまで回復している。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の38道府県から35道府県に減少し、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年に引き続きゼロとなった。ちなみに、東京は+2.1%(前年分+1.8%)、大阪は+0.5%(同+0.3%)。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は21都市(昨年18都市)、横ばいは14都市(同8都市)、下落は12都市(同21都市)に減少。このうち上昇率「5%以上」は10都市(同8都市)に、また、上昇率「5%未満」は11都市(同10都市)に増えた。上昇要因には、オリンピックの開催決定やリニア中央新幹線事業の着工による今後の開発への期待、主要ターミナル前の大型商業施設等のオープン、都市再開発などがある。
今年1月1日時点の全国約32万9千地点(継続地点)における標準宅地の前年比の変動率の平均は▲0.4%下落し、7年連続の下落となった。しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分からは3.1%→2.8%→1.8%→0.7%→0.4%と、5年連続で着実に下げ幅は縮小傾向をたどっている。
都道府県別の路線価をみると、標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値の上昇率が「5%未満」の都道府県は、昨年分の1都1府・6県から1都2府7県に増え、滋賀県、福岡県も横ばいまで回復している。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の38道府県から35道府県に減少し、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年に引き続きゼロとなった。ちなみに、東京は+2.1%(前年分+1.8%)、大阪は+0.5%(同+0.3%)。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は21都市(昨年18都市)、横ばいは14都市(同8都市)、下落は12都市(同21都市)に減少。このうち上昇率「5%以上」は10都市(同8都市)に、また、上昇率「5%未満」は11都市(同10都市)に増えた。上昇要因には、オリンピックの開催決定やリニア中央新幹線事業の着工による今後の開発への期待、主要ターミナル前の大型商業施設等のオープン、都市再開発などがある。
投稿者:
2015.07.01更新
【TAO通信】国税不服審判所への審査請求が過去最小に
国税庁・国税不服審判所が公表した2014年度における不服の申立て及び訴訟の概要によると、税務署に対する異議申立ての発生件数は、消費税を始めほとんどの税目が増加し、全体では1951年以降で最少だった前年度から16.8%増の2755件となった。処理件数では、「一部取消」189件、「全部取消」67件と納税者の主張が一部でも認められたのは256件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を0.7ポイント下回る9.3%だった。
また、税務署の処分(異議決定)を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等が大幅に減少したことなどから、28.9%減の2030件と、調査を開始した1970年度以降で最少となった。処理件数では、「一部取消」122件、「全部取消」117件で、納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同0.3ポイント増の8.0%となった。
一方、訴訟となった発生件数は、多くの税目で減少したことから、前年度を18.3%下回る237件だった。終結件数では、「国の一部敗訴」6件、「同全部敗訴」13件で、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同0.5ポイント減の6.8%となっている。
このような納税者救済・勝訴割合は、あくまでも結果論だが、全体でみると、2014年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは514件で、処理・訴訟の終結件数の合計6005件に占める割合は8.6%と、前年度から横ばいで推移している。
また、税務署の処分(異議決定)を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等が大幅に減少したことなどから、28.9%減の2030件と、調査を開始した1970年度以降で最少となった。処理件数では、「一部取消」122件、「全部取消」117件で、納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同0.3ポイント増の8.0%となった。
一方、訴訟となった発生件数は、多くの税目で減少したことから、前年度を18.3%下回る237件だった。終結件数では、「国の一部敗訴」6件、「同全部敗訴」13件で、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同0.5ポイント減の6.8%となっている。
このような納税者救済・勝訴割合は、あくまでも結果論だが、全体でみると、2014年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは514件で、処理・訴訟の終結件数の合計6005件に占める割合は8.6%と、前年度から横ばいで推移している。
投稿者:
2015.06.24更新
【TAO通信】復興特別所得税の記載漏れが大幅減少
国税庁のまとめによると、2014年分所得税等の確定申告における復興特別所得税の記載漏れ申告者は、約7万人と前年度分の確定申告より減少したことが分かった。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の創設に伴い設けられたもので、2013年から2037年までの確定申告については、所得税及び復興特別所得税を併せて申告・納付することとされている。
しかし、最初の申告となった2013年分確定申告では、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax(国税電子申告・納税システム)などを利用せず、手書きにより申告書を提出した約980万人のうち約4.7%に当たる約45.7万人が「復興特別所得税」の欄への記載漏れ(空白のまま)だったことが明らかになり、国税当局が記載漏れの申告者に対して、昨年末まで行政指導などの是正措置を図ってきた。
このようなことから、国税当局は2014年分所得税等確定申告に際しても、同庁ホームページ等を通じて復興特別所得税の記載漏れがないよう周知を行ってきた。2014年分確定申告では、その効果もあり2139.1万人の所得税等申告人員の0.7%に当たる手書き申告書提出者(約900万人)のうち、記載漏れ申告者は約7万人と前年分の6分の1弱まで減少し、記載漏れ割合も0.7%まで低下した。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の創設に伴い設けられたもので、2013年から2037年までの確定申告については、所得税及び復興特別所得税を併せて申告・納付することとされている。
しかし、最初の申告となった2013年分確定申告では、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax(国税電子申告・納税システム)などを利用せず、手書きにより申告書を提出した約980万人のうち約4.7%に当たる約45.7万人が「復興特別所得税」の欄への記載漏れ(空白のまま)だったことが明らかになり、国税当局が記載漏れの申告者に対して、昨年末まで行政指導などの是正措置を図ってきた。
このようなことから、国税当局は2014年分所得税等確定申告に際しても、同庁ホームページ等を通じて復興特別所得税の記載漏れがないよう周知を行ってきた。2014年分確定申告では、その効果もあり2139.1万人の所得税等申告人員の0.7%に当たる手書き申告書提出者(約900万人)のうち、記載漏れ申告者は約7万人と前年分の6分の1弱まで減少し、記載漏れ割合も0.7%まで低下した。
投稿者:
2015.06.18更新
【TAO通信】進むICTを利用した確定申告推進
2014年分所得税等の確定申告においては、所得税の申告書提出件数が2139万1千件で6年連続の減少となり、過去最高だった2008年分(2369万3千件)を9.7%下回っているものの、それでも2千万件を超えている。
こうした2千万人を超える納税者数に対応するために、国税庁は、確定申告における基本方針として、「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいる。国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1209万3千人にのぼり、2013年分より3.9%増加。所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は前年より2.2ポイント上昇の56.5%に達した。贈与税の申告でも、提出人員51万9千人のうち56.8%(29万5千人)がICTを利用、前年分から10.6%の増加となっている。
署でのICT利用は、署のパソコンで申告書を作成して「e-Tax」が451万1千人、同「書面での提出」が44万7千人の計495万9千人と、前年分に比べ0.7%減少。自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成して書面での提出」が323万2千人、「同e-Tax」が62万1千人、「民間の会計ソフトで申告書を作成してe-Tax」が328万1千人の計713万4千人で同7.4%増となり、ともに順調に増加している。
こうした2千万人を超える納税者数に対応するために、国税庁は、確定申告における基本方針として、「自書申告」を推進、そのためのICT(情報通信技術)を活用した施策に積極的に取り組んでいる。国税庁のホームページ上で申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxなど、ICTを利用した所得税の確定申告書の提出人員は全体で1209万3千人にのぼり、2013年分より3.9%増加。所得税の確定申告書の提出人員に占める割合は前年より2.2ポイント上昇の56.5%に達した。贈与税の申告でも、提出人員51万9千人のうち56.8%(29万5千人)がICTを利用、前年分から10.6%の増加となっている。
署でのICT利用は、署のパソコンで申告書を作成して「e-Tax」が451万1千人、同「書面での提出」が44万7千人の計495万9千人と、前年分に比べ0.7%減少。自宅などでのICT利用は、「HP作成コーナーで申告書を作成して書面での提出」が323万2千人、「同e-Tax」が62万1千人、「民間の会計ソフトで申告書を作成してe-Tax」が328万1千人の計713万4千人で同7.4%増となり、ともに順調に増加している。
投稿者:
2015.06.10更新
【TAO通信】所得税申告納税額が4年ぶりの減少
国税庁が発表した2014年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は、前年比0.2%減の2139万1千人と、6年連続で減少した。申告納税額がある人(納税人員)は同1.6%減の612万人、その所得金額も同3.6%下回る37兆1054億円と、ともに3年ぶりに減少した。
申告納税額は、前年を6億円下回る2兆7087億円と、微減ながら4年ぶりの減少となった。これは、株式などの譲渡所得が前年分に比べ55%減と大幅に減ったことが影響しているとみられている。
所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分に比べ14.7%減の93万人7千人と2年ぶりに減少し、うち所得金額がある人は同30.3%減の46万1千人、所得金額は同55.0%減の2兆1759億円と、ともに大幅に減少した。これは、前年の2013年末で株式譲渡益への軽減税率の適用が廃止されたことから、2013年分が"駆込み"で過去最高となった反動とみられている。
一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は51万9千人で同5.6%増加、そのうち納税人員は36万6千人で同11.1%増加し、その申告納税額は2803億円で、同63.1%増と大幅に増加した。
これは、2014年度相続税改正において今年1月から課税ベースが拡大し最高税率も上がったことなどから、2014年は改正前に贈与する人が増えたとみられている。
申告納税額は、前年を6億円下回る2兆7087億円と、微減ながら4年ぶりの減少となった。これは、株式などの譲渡所得が前年分に比べ55%減と大幅に減ったことが影響しているとみられている。
所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分に比べ14.7%減の93万人7千人と2年ぶりに減少し、うち所得金額がある人は同30.3%減の46万1千人、所得金額は同55.0%減の2兆1759億円と、ともに大幅に減少した。これは、前年の2013年末で株式譲渡益への軽減税率の適用が廃止されたことから、2013年分が"駆込み"で過去最高となった反動とみられている。
一方、贈与税の申告状況をみると、贈与税の申告書を提出した人員は51万9千人で同5.6%増加、そのうち納税人員は36万6千人で同11.1%増加し、その申告納税額は2803億円で、同63.1%増と大幅に増加した。
これは、2014年度相続税改正において今年1月から課税ベースが拡大し最高税率も上がったことなどから、2014年は改正前に贈与する人が増えたとみられている。
投稿者:
2015.06.03更新
【TAO通信】「空き家対策特措法」が全面施行
適切な管理が行われていない空き家等が治安や防災、衛生、景観などの観点から地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている。こうしたことから、居住実態のない空き家を自治体が取り壊したりすることができるようにする「空き家対策特別措置法」が5月26日に、全面施行される。
固定資産税の住宅特例対象から除外する措置を盛り込んだことで、問題が解消の方向に向かうことが期待されている。
総務省の統計によると、2013年の全国の空き家総数は2008年から63万戸増えて820万戸と急激に増加。人口減少社会の反映とも言えるが、長年、適正な管理がされていない危険な住宅が崩壊したり、放火されたりする例が増加して社会問題化したことで特措法が制定された。居住していない所有者にとっては、取壊しによる高額な費用の工面や更地化すると固定資産税の住宅特例が適用されなくなることが放置の理由とされてきた。
そこで今回、国が空き家対策の要としたのが、固定資産税の住宅用地特例の適用除外だ。現在、200平方メートル以下の部分は固定資産税の税額が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1になっているが、今回の措置によって、市町村が「特定空き家」と認定した場合は、特例が適用されなくなるとともに、立入調査したり、指導、勧告、命令、さらには取り壊すなどの行政代執行も可能になった。
固定資産税の住宅特例対象から除外する措置を盛り込んだことで、問題が解消の方向に向かうことが期待されている。
総務省の統計によると、2013年の全国の空き家総数は2008年から63万戸増えて820万戸と急激に増加。人口減少社会の反映とも言えるが、長年、適正な管理がされていない危険な住宅が崩壊したり、放火されたりする例が増加して社会問題化したことで特措法が制定された。居住していない所有者にとっては、取壊しによる高額な費用の工面や更地化すると固定資産税の住宅特例が適用されなくなることが放置の理由とされてきた。
そこで今回、国が空き家対策の要としたのが、固定資産税の住宅用地特例の適用除外だ。現在、200平方メートル以下の部分は固定資産税の税額が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1になっているが、今回の措置によって、市町村が「特定空き家」と認定した場合は、特例が適用されなくなるとともに、立入調査したり、指導、勧告、命令、さらには取り壊すなどの行政代執行も可能になった。
投稿者:
2015.05.27更新
【TAO通信】記念品として支給する旅行券に注意
創業記念や永年勤続表彰などで支給する記念品が給与として課税されないためには、(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること、(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること、(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること、との全ての要件を満たす必要がある。記念品の支給や旅行への招待費用に代えて現金、商品券などを支給する場合は、その全額が給与課税され、また、本人が自由に記念品を選択できる場合も、その記念品の価額が給与課税される。
特に、旅行券の支給には注意したい。一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になるので、原則として給与等として課税される。
ただし、課税されない要件がある。それは、(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること、(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること、(3)旅行券の支給を受けた者がその旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行者等への支払額)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社へ提出すること、などの要件を満たしている場合は、給与等として課税しなくても差し支えないとされている。
特に、旅行券の支給には注意したい。一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になるので、原則として給与等として課税される。
ただし、課税されない要件がある。それは、(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること、(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること、(3)旅行券の支給を受けた者がその旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行者等への支払額)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社へ提出すること、などの要件を満たしている場合は、給与等として課税しなくても差し支えないとされている。
投稿者:
2015.05.20更新
【TAO通信】国の借金、3月末で1053兆円
財務省がこのほど公表した2015年3月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は1053兆3572億円にのぼり、過去最大を更新した。2014年度末(昨年3月末)からは28兆4003億円増加し、初めて1千兆円の大台を突破した2013年6月末以降、借金の膨張が止まらない。
2014年3月末に比べ、国債は約27.7兆円増の約881.5兆円で全体の約84%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約30.2兆円増の約774.1兆円(うち復興債が約8.3兆円)と過去最高を更新した。また、一時的な資金繰りに充てる政府短期証券は約1.2兆円増の約116.9兆円と増加したが、財政投融資特別会計国債は約5.2兆円減の約99.0兆円、借入金は約0.5兆円減の約55.0兆円といずれも減少している。
この「国の借金」1053兆3572億円は、2015年度一般会計提出予算の歳出総額96兆3420億円の約11倍、同年度税収見込み額54兆5250億円の約19倍である。年収500万円のサラリーマンが9500万円の借金を抱えている勘定だ。
また、わが国の今年4月1日時点での推計人口1億2691万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、2014年3月末時点の約806万円から約830万円に上昇する。
なお、2015年度末の国の借金は、3月末実績の約1053.4兆円からさらに約113.7兆円増えて1167.1兆円になる見通し。
2014年3月末に比べ、国債は約27.7兆円増の約881.5兆円で全体の約84%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約30.2兆円増の約774.1兆円(うち復興債が約8.3兆円)と過去最高を更新した。また、一時的な資金繰りに充てる政府短期証券は約1.2兆円増の約116.9兆円と増加したが、財政投融資特別会計国債は約5.2兆円減の約99.0兆円、借入金は約0.5兆円減の約55.0兆円といずれも減少している。
この「国の借金」1053兆3572億円は、2015年度一般会計提出予算の歳出総額96兆3420億円の約11倍、同年度税収見込み額54兆5250億円の約19倍である。年収500万円のサラリーマンが9500万円の借金を抱えている勘定だ。
また、わが国の今年4月1日時点での推計人口1億2691万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、2014年3月末時点の約806万円から約830万円に上昇する。
なお、2015年度末の国の借金は、3月末実績の約1053.4兆円からさらに約113.7兆円増えて1167.1兆円になる見通し。
投稿者:
2015.05.13更新
【TAO通信】ふるさと納税、高額品には自粛要請
ふるさと納税制度が4月から改正された。「控除の拡大」で寄付金の上限が増え、手続きも簡素化されたのが特徴で、多くの自治体で特色のある「返礼品」に知恵を絞れば、それを見つけて寄付をしようと両者は過熱気味。控除の拡大で、これまで上限額は個人住民税の約1割だったが約2割に増えた。また控除を受けるには税務署で確定申告が必要だったが、4月以降は年間5自治体までの寄付ならば確定申告が原則必要なくなった。
第一次安倍政権で始まったこの制度は2011年の東日本大震災で利用が増えた。しかし多くの自治体は被災地応援に回り制度拡大の独自路線は避けてきた。そこにアベノミクスの「地方創生」で頑張る自治体を税制面で応援する姿勢に変わった。自治体が返礼品に特産物を贈れば地場産業のてこ入れにもつながるからだ。
ところが品物が高額化する一方に総務省は釘を刺す。換金性の高いプリペイドカード、寄付額に対して返礼の割合が高い品物などを「自粛」するよう通知。宅地、宮崎牛一頭分、純金手裏剣、電子マネー等は、話題や物議をかもした。「通販みたいで国策としていかがなものか」と石破茂地方創生相も渋い表情だ。南高梅「白干し」(樽詰め―田辺市)や船橋市の「ふなっしーと船えもん」(特製クリアファイル)などは豪奢を押さえ工夫も見られるが...。(「ふるさと納税情報センター」で情報公開中)
第一次安倍政権で始まったこの制度は2011年の東日本大震災で利用が増えた。しかし多くの自治体は被災地応援に回り制度拡大の独自路線は避けてきた。そこにアベノミクスの「地方創生」で頑張る自治体を税制面で応援する姿勢に変わった。自治体が返礼品に特産物を贈れば地場産業のてこ入れにもつながるからだ。
ところが品物が高額化する一方に総務省は釘を刺す。換金性の高いプリペイドカード、寄付額に対して返礼の割合が高い品物などを「自粛」するよう通知。宅地、宮崎牛一頭分、純金手裏剣、電子マネー等は、話題や物議をかもした。「通販みたいで国策としていかがなものか」と石破茂地方創生相も渋い表情だ。南高梅「白干し」(樽詰め―田辺市)や船橋市の「ふなっしーと船えもん」(特製クリアファイル)などは豪奢を押さえ工夫も見られるが...。(「ふるさと納税情報センター」で情報公開中)
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)