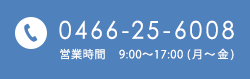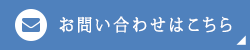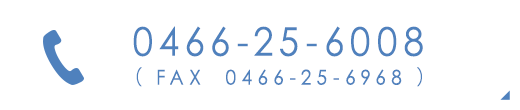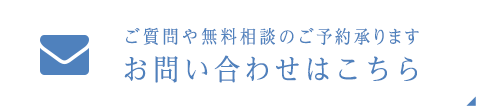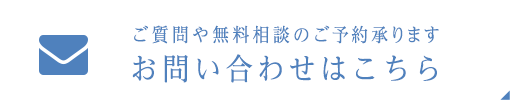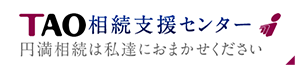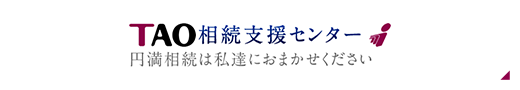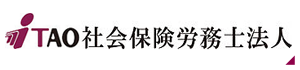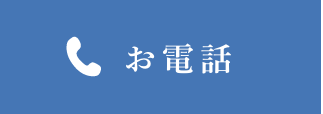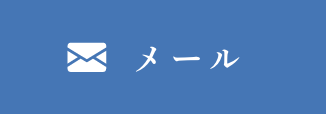2015.09.16更新
国税庁はこのほど、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度に基づいて割り振る法人番号の発送を10月22日からスタートすると発表した。
国税庁が指定した13桁の法人番号を記載した法人番号指定通知書は、設立登記法人の場合、東京都千代田区、中央区、港区に本店がある企業からスタートし、企業の所在地の都道府県単位(東京都については3つに区分)で10月22日から11月25日までの間、7回に分けて全440万団体へ発送する。
設立登記のない法人については、11月13日に全国一斉発送し、公表については11月17日に行う予定。また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定となっている。
法人番号は個人番号と異なり、広く一般への利用を前提にしていることから、10月5日にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、企業への法人番号指定通知後、同月26日から基本3情報である(1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所所在地、(3)法人番号、を順次公表する。
法人番号は、会社登記をした全ての企業に付される13桁の数字で、国の機関や地方公共団体も付番対象となる。2016年1月以降に提出する確定申告書や法定調書に記載が求められる。
投稿者: TAO税理士法人
2015.09.09更新
経済産業省は、2016年度税制改正に向けて、(1)未来投資を拡大する成長志向の法人税改革や、(2)地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化、などを掲げた要望書を公表した。
(1)では、法人実効税率の早期の20%台引下げや、企業経営者に「攻めの経営」を促すため、コーポレートガバナンスが強化されている上場企業等を対象に、役員給与における多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を促進することを求めている。
安倍政権は、法人実効税率を数年内に20%台に引き下げる方針で、2015年度は33.06%(標準税率32.11%)に、2016年度は32.26%(同31.33%)に引き下げることが決まっているが、経産省は、2016年度に税率引下げ幅のさらなる上乗せを図り、早期に20%台までの引下げを目指す考えだ。
(2)の地域経済再生、中小企業・小規模事業者の活性化では、新たな機械装置等の投資に係る固定資産税の見直しや、外国人旅行者向けの消費税免税店・旅行消費額の拡大を促すため、免税の対象となる、一般物品の最低購入額を「1万円超」から「5000円以上」に引き下げることなどを要望。
このほか、中小企業者等が30万円未満の設備を取得した場合、合計300万円まで、取得価額を損金算入できる少額減価償却資産の特例措置の延長や、中小法人の交際費支出800万円まで全額損金算入できる交際費課税の特例措置の延長などを盛り込んでいる。
投稿者: TAO税理士法人
2015.09.02更新
2015年度税制改正の一環として「国税スキャナ保存制度」が抜本的に見直されたが、この新しいスキャナ保存制度の適用申請日が約1ヵ月後に迫っている。スキャナ保存制度とは、一定要件を満たせば契約書や領収書などの国税関係書類をスキャナ保存することを認める制度。ペーパーレスとなる上に、紙での保存の煩雑な作業や人的コストが解消するため、地味ながら人気のある制度だ。2015年度税制改正では同制度が大幅に緩和され、スキャナ保存の対象となる契約書及び領収書に係る金額基準(現行3万円)が廃止され、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ保存ができるようになる。
ただし、契約書や領収書、資金移動等直結書類(納品書・約束手形等)の重要書類については、適正な事務処理の実施を担保する規定の整備と、これに基づき事務処理を実施していることをスキャナ保存に係る新たな要件とすることとされる。
重要書類以外の見積書や注文書等の一般書類についても、スキャナで読み取る際に必要とされているその書類の大きさに関する情報の保存を不要とするとともに、カラーでの保存を不要とし、白黒での保存でも要件を満たすこととされるなど、要件が緩和される。新制度の適用は2016年1月からで、スキャナ保存の申請は開始日の3ヵ月前までに行う必要があるため、2015年9月30日に申請書を提出すれば、適用開始日である来年1月1日から新制度を適用できる。
投稿者: TAO税理士法人
2015.08.26更新
改正地域再生法が8月10日から施行され、地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度がスタートするとともに、特定の事業用資産の買換え特例のうち、いわゆる9号買換え特例の課税繰延べ割合の縮減の適用が始まった。9号買換えとは、個人又は法人が、所有期間10年を超える土地等、建物等を譲渡して、新たに事業用の一定の土地等、建物等、機械装置等を取得した場合、譲渡益の80%相当額について課税を繰り延べるというもの。
2015年度税制改正において創設された地方拠点強化税制は、集中地域(3大都市圏と東京23区)以外で事業用資産を譲渡し、集中地域で買換え資産を取得した場合には課税繰延べ割合が引き下げられる。例えば、3大都市圏への買換えの場合、課税繰延べ割合は80%から75%に、東京23区への買換えの場合は70%に引き下げられる。ただし、施行日前に事業用資産の譲渡又は買換え資産の取得をしていれば、旧法の80%が適用される。
地方拠点強化税制は、拡充型と移転型があり、移転型では、例えば、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を東京23区や3大都市圏以外の地方へ移転した場合には税制優遇措置が受けられる。
具体的には、(1)移転先で取得したオフィスに係る建物・建物付属設備・構築物の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%、(2)移転先で新たに雇用した従業員1人当たり最大80万円を税額控除する。
投稿者: TAO税理士法人
2015.08.13更新
個人が法人に資産を無償で贈与する、例えば、社長が、自分が所有する土地を会社に贈与するケースは珍しくない。社長が会社に土地を贈与するということだから、資産を譲り受けた会社に税金が発生するのは想像できるが、贈与する側の社長には税金がかからないように思える。
しかし、資産を個人が法人へ贈与した場合には、その時の資産の時価に相当する金額で譲渡があったものとみなすという規定が所得税法59条にある。いわゆるみなし譲渡所得課税と呼ばれるものである。例えば、社長の土地の購入時の価額が2000万円で、贈与時の時価が3000万円であれば、3000万円から2000万円を差し引いた値上がり益の1000万円が譲渡所得となり、税
金が発生することになる。
一方で、会社の取扱いだが、法人が贈与を受けた場合には、その無償で譲り受けた財産の時価相当額の受贈益を認識する必要があり、その取得した事業年度の益金の額に算入する必要がある。上記の例では、社長所有の土地の時価が3000万円だから、法人は3000万円の受贈益を認識しなければならない。
法人税法上、法人が他の者と取引を行う場合には、有償無償を問わず、全ての資産は時価によって取引されたものとみなして課税所得を計算するというのが原則的な取扱いになっている。
したがって、個人が無償で譲渡した場合は、通常の譲渡だったら収入となっただろう金額=時価をその法人の益金の額に算入(収益)する必要がある。
投稿者: TAO税理士法人
2015.08.05更新
被相続人の死亡によって被相続人の勤め先等の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象となる。
これ以外の部分は、被相続人の死亡が、(1)業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当額 、(2)業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)相当額が、「弔慰金に相当する金額」として非課税となる。これを超えた場合は、その部分に相当する金額が退職手当金等として相続税の課税対象となるので、注意したい。
この弔慰金等には上記のように非課税枠があるので有効活用ができる。
例えば、被相続人の役員報酬が150万円/月(賞与を除く)、死亡原因が非業務上のケースで、死亡退職金6000万円で弔慰金がゼロの場合は、当然ながら死亡退職金6000万円全額が課税対象となる。
しかし、死亡退職金5000万円と弔慰金1000万円に分けてもらった場合は、弔慰金の非課税枠が「150万円×6ヵ月=900万円」があり、退職金としての課税対象額は「1000万円-900万円=100万円」となり、死亡退職金5000万円+100万円の計5100万円が課税対象となる。このように、「退職金」だけでもらう場合と「退職金と弔慰金」に分けてもらう場合とでは、相続財産としての課税対象が900万円も違ってくるので、有効活用したい。
投稿者: TAO税理士法人
2015.07.29更新
政府・与党が、遺言に基づいた相続について相続税を軽減する方向で検討を進めている。自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は、有効な遺言に基づいて相続が行われた場合に、従来からある基礎控除に上乗せする形で一定額を控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。
気になる控除額は「数百万円」の規模で検討される見込み。遺言による遺産分割を促し、遺産相続をめぐるトラブルを防止、若い世代へのスムーズな資産移転を図る狙いがある。
相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引き、残額に税率を掛けて計算する仕組み。基礎控除額は、昨年末まで「5千万円+法定相続人数×1千万円」だったが、今年1月から「3千万円+法定相続人数×600万円」に引き下げられている。
この基礎控除の大幅な引下げにより、これまで相続税とは無縁だった中間層も取り込まれることになった。法定相続人が1人のケースでは、遺産総額が3600万円を超えると相続税の課税対象となる。昨年末までは「6千万円超」だったため、相続税がグッと身近になった感がある。
新たに相続税の対象となった層は、相続対策に対する十分な備えがないケースが多く、遺産分割などをめぐるトラブル増加も懸念されることから、新控除の創設で遺言促進による円滑な資産移転を促したい考えだ。自民党は、党税制調査会に提言して早ければ2017年度税制改正での導入を目指す考えだ。
投稿者: TAO税理士法人
2015.07.23更新
国税庁がまとめた2014年度相続税の物納申請状況等によると、今年3月までの1年間の物納申請件数は209件で前年度比28.1%減となったが、金額では大口案件があったため同262.0%増の286億円と大幅増加。件数は5年連続の減少、金額は5年ぶりの増加となった。
物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、それまで年間400~500件程度に過ぎなかったものが、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落で、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度に1238件、1991年度に3871件、そして1992年度には1万2千件台まで急増した。
しかしその後は、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少。2014年度も5年連続の減少となっており、2014年度の申請件数はピーク時1992年度(1万2778件)のわずか0.9%、金額でも同じくピーク時1992年度(1兆5645億円)の0.2%にまで減少している。
一方、処理状況をみると、前年度からの処理未済を含め前年度比34.2%減の131件、金額では同306.8%増の301億円を処理した。金額は大口案件があったため。処理の内訳は、全体の7割強の88件が許可されて財務局へ引き渡され、物納財産として不適格として18件が却下、残りの25件は納税者自らが物納申請を取り下げている。
投稿者: TAO税理士法人
2015.07.17更新
7月8日(水)に、当事務所で「経営計画策定会」を開催いたしました。2社の関与先の代表取締役が、丸一日かけて、経営コンサルタント等のアドバイスを受けながら、自社の問題点、改善点を洗い出し、今後の会社の経営方針、経営計画を策定しました。 「普段頭の中で考えていたことを吐き出して、整理することができた。」、「自社のことを、じっくり考える時間がなかなか持てなかったので、こういう機会があって良かった。」等の感想をいただきました。
「経営計画策定会」は、今年あと2回開催する予定です。当税理士法人は、今後も会社の発展のための企画を提供をしていきたいと思います。
投稿者: TAO税理士法人
2015.07.17更新
当法人では、毎年7月に夏期研修を行っており、今年は7月10日、11日の2日間で実施しました。
今年は全職員が参加し、法人税、源泉所得税、印紙税など日常業務に関連する項目のほか、資産税、国際税務などについての研修を行いました。
投稿者: TAO税理士法人