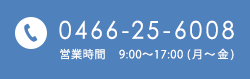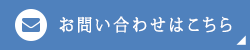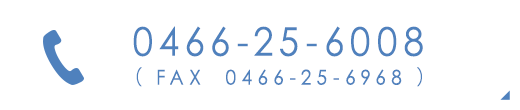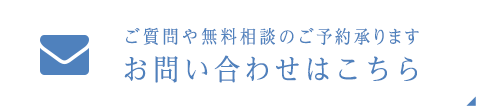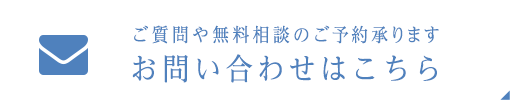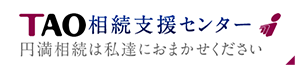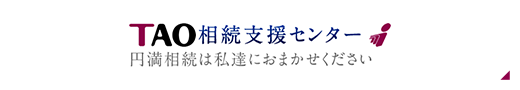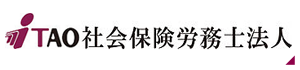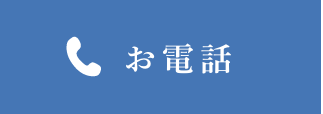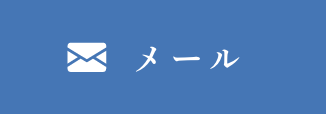今年6月までの1年間(2013事務年度)における法人の黒字申告割合は29.1%で3年連続増加したが、低水準は変わらず7割強の法人が赤字だ。このような状況に便乗して実際は黒字なのに赤字を装う企業が後を絶たない。同事務年度中に法人税の実地調査をした9万1件のうち4割近い3万5千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強(12%)の約4千社が実際は黒字だったことが、国税庁のまとめで判明した。
調査結果によると、実地調査した3万5千件のうち、約7割に当たる2万4千件から総額2809億円にのぼる申告漏れ所得金額を見つけ、加算税51億円を含む261億円の税額を追徴した。調査1件当たりの申告漏れ所得は808万円となる。
また、実施調査したうちの22.8%の8千件は仮装・隠ぺいなど故意に所得をごまかしており、その不正脱漏所得金額総額は986億円にのぼった。不正申告1件当たりの不正脱漏所得は1245万円。
2013事務年度の無所得申告法人調査は、前年度に引き続き改正国税通則法の影響で1件当たりの調査日数が増えたことから、実地調査件数はやや減少している。それでも、黒字転換した法人は前年度とほぼ同様の約4千社あったわけだが、調査で把握された1件当たり申告漏れ所得金額は808万円とかなり高額だ。
ここに、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する背景がある。
2014.11.12更新
【TAO通信】法人の申告漏れ、前年度比25%減
国税庁がこのほど公表した今年6月までの1年間(2013事務年度)における法人税調査事績によると、不正計算が想定されるなど調査必要度の高い9万1千法人(前年度比2.8%減)を実地調査した結果、うち約73%にあたる6万6千件(同3.2%減)から前年度に比べ24.8%減の総額7515億円の申告漏れを見つけた。追徴税額は1591億円(同24.2%減)。1件あたりの申告漏れ所得は同22.6%減の829万円となる。
実地調査件数は、改正国税通則法の施行に伴い、昨年度から、課税理由の説明などの原則義務化で事務作業量が増加し、1件当たりの調査期間が伸びた影響が今事務年度も続いている。また、調査した18.6%(不正発見割合)に当たる1万7千件(前年度比1.6%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比20.8%減の2184億円、1件当たりでは同19.5%減の1298万円となった。
不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が47.3%で12年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位(唯一2001年度がワースト2位)という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、前年4位の「自動車修理」(29.8%)、同2位の「パチンコ」(29.0%)、同5位の「廃棄物処理」(28.4%)、同3位の「土木工事」(28.2%)の順で続く。
実地調査件数は、改正国税通則法の施行に伴い、昨年度から、課税理由の説明などの原則義務化で事務作業量が増加し、1件当たりの調査期間が伸びた影響が今事務年度も続いている。また、調査した18.6%(不正発見割合)に当たる1万7千件(前年度比1.6%減)が故意に所得を仮装・隠ぺいするなどの不正を行っており、その不正脱漏所得は前年度比20.8%減の2184億円、1件当たりでは同19.5%減の1298万円となった。
不正を業種別(調査件数350件以上)にみると、不正発見割合の高い10業種では、「バー・クラブ」が47.3%で12年連続のワースト1位。「バー・クラブ」は、近年25年間で24回1位(唯一2001年度がワースト2位)という不名誉な記録を持つワースト業種の常連。以下、前年4位の「自動車修理」(29.8%)、同2位の「パチンコ」(29.0%)、同5位の「廃棄物処理」(28.4%)、同3位の「土木工事」(28.2%)の順で続く。
投稿者:
2014.11.05更新
【TAO通信】所得税調査で8216億円の申告漏れ把握
国税庁によると、個人に対する今年6月までの1年間(2013事務年度)の所得税調査は、前年度に比べ31.8%増の89万9千件行われた。そのうち、約66%に当たる59万件から8216億円の申告漏れ所得を見つけた。その追徴税額は1020億円。1件平均91万円の申告漏れに対し11万円を追徴した。
実地調査における特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)は4万6千件行われ、うち約85%にあたる3万9千件から総額3702億円の申告漏れ所得を見つけ、665億円を追徴。件数では全体の5.1%に過ぎないが、申告漏れ所得金額全体の45.1%を占めた。調査1件あたりの申告漏れは810万円と、全体の平均91万円を大きく上回る。
また、実地調査に含まれる着眼調査(資料情報や事業実態の解明を通じて行う短期間の調査)は1万6千件行われ、うち1万2千件から436億円の申告漏れを見つけ、32億円を追徴。1件あたり平均申告漏れは273万円。一方、簡易な接触は、83万7千件行われ、うち54万件から4078億円の申告漏れを見つけ324億円を追徴。1件あたりの平均申告漏れは49万円だった。
実地調査トータルでは、6万1千件の調査を行い、うち5万1千件から4137億円の申告漏れを見つけ、696億円を追徴している。つまり、実地調査件数は全体の6.8%に過ぎないが、申告漏れ所得全体の5割(50.4%)を把握していることになる。
実地調査における特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)は4万6千件行われ、うち約85%にあたる3万9千件から総額3702億円の申告漏れ所得を見つけ、665億円を追徴。件数では全体の5.1%に過ぎないが、申告漏れ所得金額全体の45.1%を占めた。調査1件あたりの申告漏れは810万円と、全体の平均91万円を大きく上回る。
また、実地調査に含まれる着眼調査(資料情報や事業実態の解明を通じて行う短期間の調査)は1万6千件行われ、うち1万2千件から436億円の申告漏れを見つけ、32億円を追徴。1件あたり平均申告漏れは273万円。一方、簡易な接触は、83万7千件行われ、うち54万件から4078億円の申告漏れを見つけ324億円を追徴。1件あたりの平均申告漏れは49万円だった。
実地調査トータルでは、6万1千件の調査を行い、うち5万1千件から4137億円の申告漏れを見つけ、696億円を追徴している。つまり、実地調査件数は全体の6.8%に過ぎないが、申告漏れ所得全体の5割(50.4%)を把握していることになる。
投稿者:
2014.10.29更新
【TAO通信】通勤手当の非課税限度額を引上げ
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっている。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、段階的に定められているが、政府は、通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令を官報に掲載した。
見直しは、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げる。具体的には、片道の通勤距離が、「10キロメートル未満」は4200円(改正前4100円)、「10キロメートル以上15キロメートル未満」は7100円(同6500円)、「15キロメートル以上25キロメートル未満」は1万2900円(同1万1300円)、「25キロメートル以上35キロメートル未満」は1万8700円(同1万6100円)、「35キロメートル以上45キロメートル未満」は2万4400円(同2万900円)に、それぞれ引き上げられる。
それとともに、45キロメートル以上は2万4500円とされていたものを、(1)「45キロメートル以上55キロメートル未満」は2万8000円、(2)「55キロメートル以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられている。
この政令は、2014年10月20日から施行され、改正後の所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、2014年4月1日以後に支給される通勤手当(新通勤手当)について適用される。
見直しは、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げる。具体的には、片道の通勤距離が、「10キロメートル未満」は4200円(改正前4100円)、「10キロメートル以上15キロメートル未満」は7100円(同6500円)、「15キロメートル以上25キロメートル未満」は1万2900円(同1万1300円)、「25キロメートル以上35キロメートル未満」は1万8700円(同1万6100円)、「35キロメートル以上45キロメートル未満」は2万4400円(同2万900円)に、それぞれ引き上げられる。
それとともに、45キロメートル以上は2万4500円とされていたものを、(1)「45キロメートル以上55キロメートル未満」は2万8000円、(2)「55キロメートル以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられている。
この政令は、2014年10月20日から施行され、改正後の所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、2014年4月1日以後に支給される通勤手当(新通勤手当)について適用される。
投稿者:
2014.10.22更新
【TAO通信】法人の黒字申告割合は3年連続の増加
国税庁がこのほど発表した2013年度の法人税の申告事績によると、今年6月末現在の法人数は前年度から0.7%増の300万7千法人で、うち2013年度内に決算期を迎え今年7月までに申告した法人は、同0.4%増の277万1千法人だった。
その申告所得金額は同17.9%(8兆906億円)増の53兆2780億円、申告税額の総額も同9.3%(9298億円)増の10兆9403億円と、ともに4年連続の増加となった。
この結果、法人の黒字申告割合は、前年度に比べ1.7ポイント上昇して29.1%となり、3年連続の増加となった。
もっとも、初めて30%を割り込んだ2008年度から2010年度(25.2%)までは、3年連続で過去最低を更新していたもので、黒字申告割合は低水準が続いている。法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から21年も続いていることになる。
4年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて10.9%増の6619万円となった。一方、申告欠損金額は、同24.1%減の12兆7744億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同22.6%減の650万円と、ともに大幅に減少し、企業業績の改善がうかがえる結果となった。ちなみに、申告所得金額のピークは2006年度の57兆828億円、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2791億円だった。
その申告所得金額は同17.9%(8兆906億円)増の53兆2780億円、申告税額の総額も同9.3%(9298億円)増の10兆9403億円と、ともに4年連続の増加となった。
この結果、法人の黒字申告割合は、前年度に比べ1.7ポイント上昇して29.1%となり、3年連続の増加となった。
もっとも、初めて30%を割り込んだ2008年度から2010年度(25.2%)までは、3年連続で過去最低を更新していたもので、黒字申告割合は低水準が続いている。法人の黒字申告割合は、過去最高だった1973年度(65.4%)の半分にも満たない低い数字が、1993年度から21年も続いていることになる。
4年連続の増加となった黒字法人の申告所得金額は、黒字申告1件あたりでは前年度に比べて10.9%増の6619万円となった。一方、申告欠損金額は、同24.1%減の12兆7744億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も同22.6%減の650万円と、ともに大幅に減少し、企業業績の改善がうかがえる結果となった。ちなみに、申告所得金額のピークは2006年度の57兆828億円、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2791億円だった。
投稿者:
2014.10.16更新
【TAO通信】年末調整で国税庁が注意を呼びかけ
国税庁はこのほど、「2014年分年末調整のしかた」を公表し、その中で年末調整を行う際に復興特別所得税の計算漏れがないよう注意を呼び掛けている。今年5月に国税庁が取りまとめた2013年分所得税確定申告においても、全申告書提出人員の2.1%にあたる約45.7万件に、復興特別所得税の税額を空欄のまま申告するなどの記載漏れがあったことなどから、改めて注意を喚起したもの。
復興特別所得税は、復興財源確保のため所得税の源泉徴収義務者に対して、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付することとされている。このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(「年調年税額」)を算出する必要があるが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことや、また、上記のように2013年分所得税確定申告においても復興特別所得税の税額の記載漏れがあったことなどから、2014年分の年末調整を前に改めて申告漏れがないよう注意を呼びかけた。
年末調整における年調年税額を計算する際には、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の年調所得税額に10.21%を乗じて算出(100円未満の端数は切捨て)する。
復興特別所得税は、復興財源確保のため所得税の源泉徴収義務者に対して、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付することとされている。このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(「年調年税額」)を算出する必要があるが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことや、また、上記のように2013年分所得税確定申告においても復興特別所得税の税額の記載漏れがあったことなどから、2014年分の年末調整を前に改めて申告漏れがないよう注意を呼びかけた。
年末調整における年調年税額を計算する際には、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の年調所得税額に10.21%を乗じて算出(100円未満の端数は切捨て)する。
投稿者:
2014.10.08更新
【TAO通信】13年分民間平均給与は3年ぶり増加
2013年1年間を通して民間企業に勤めた給与所得者の平均給与は413万6千円で、前年に比べ1.4%(5万6千円)増加したことが、国税庁がこのほど発表した2013年分民間給与の実態統計調査で分かった。平均給与は3年ぶりの増加。
調査結果によると、2013年12月31日現在の給与所得者数は、前年に比べ2.1%(113万3千人)増加の5535万4千人だった。そのうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比2.0%増の4645万4千人(正規3055万6千人、非正規1039万7千人)で過去最多となった。
その平均給与413万6千円の内訳は、平均給料・手当が同1.1%増の352万7千円と3年ぶりの増加、賞与は同3.2%増の60万9千円と2年ぶりの増加。平均給料・手当に対する平均賞与の割合は前年から0.4ポイント増の17.3%となった。
男女別の平均給与は、男性が前年比1.9%増の511万3千円、女性が同1.4%増の271万5千円。正規、非正規別にみると、1人当たりの平均給与は、正規が同1.2%増の473万円と増えたが、非正規は同0.1%減の167万8千円と減った。
平均給与を業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が696万円と突出して最も高く、「金融業、保険業」の617万円、「情報通信業」の592万円が続き、対して最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の233万円、「農林水産・鉱業」の289万円、「サービス業」の339万円となっている。
調査結果によると、2013年12月31日現在の給与所得者数は、前年に比べ2.1%(113万3千人)増加の5535万4千人だった。そのうち、1年を通じて勤務した給与所得者数は、前年比2.0%増の4645万4千人(正規3055万6千人、非正規1039万7千人)で過去最多となった。
その平均給与413万6千円の内訳は、平均給料・手当が同1.1%増の352万7千円と3年ぶりの増加、賞与は同3.2%増の60万9千円と2年ぶりの増加。平均給料・手当に対する平均賞与の割合は前年から0.4ポイント増の17.3%となった。
男女別の平均給与は、男性が前年比1.9%増の511万3千円、女性が同1.4%増の271万5千円。正規、非正規別にみると、1人当たりの平均給与は、正規が同1.2%増の473万円と増えたが、非正規は同0.1%減の167万8千円と減った。
平均給与を業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が696万円と突出して最も高く、「金融業、保険業」の617万円、「情報通信業」の592万円が続き、対して最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」の233万円、「農林水産・鉱業」の289万円、「サービス業」の339万円となっている。
投稿者:
2014.10.01更新
【TAO通信】空き家対策に固定資産税を見直しか
国土交通省及び総務省は、市町村による空き家対策を促進する観点から、2015年度税制改正に向けて、対象土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずるよう税制改正要望に盛り込んだ。
総務省の調査によると、適切な管理がなされないまま放置されて空き家となった住宅は、2013年現在、全国で820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と、ともに過去最高となっている。地方自治体においても、所有者に空き家の適正管理や撤去を促す条例を次々に制定・施行している。その数は今年4月時点で355件にのぼり、一部自治体では行政代執行で取壊しを行う例も出ているが、決定打にはなっていないのが実情だ。国交省や総務省は、事態が改善しない理由の一つに固定資産税の住宅用地に対する軽減特例があるとみている。現在、特例は面積200平方メートルまでの小規模住宅用地の価格は6分の1に、200平方メートルを超える一般住宅用地の価格は3分の1に抑えられている。つまり、住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまう。
今回の両省における税制改正要望では、「土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずる」としたが、具体的な記述はない。必要な措置としては、自主的な空き家の除去等に対して一定期間、固定資産税を減免することや、除去等をしない空き家は住宅用地の軽減特例の対象から外すなどの措置が考えられ、所有者に早期撤去などを促すとみられる。
総務省の調査によると、適切な管理がなされないまま放置されて空き家となった住宅は、2013年現在、全国で820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と、ともに過去最高となっている。地方自治体においても、所有者に空き家の適正管理や撤去を促す条例を次々に制定・施行している。その数は今年4月時点で355件にのぼり、一部自治体では行政代執行で取壊しを行う例も出ているが、決定打にはなっていないのが実情だ。国交省や総務省は、事態が改善しない理由の一つに固定資産税の住宅用地に対する軽減特例があるとみている。現在、特例は面積200平方メートルまでの小規模住宅用地の価格は6分の1に、200平方メートルを超える一般住宅用地の価格は3分の1に抑えられている。つまり、住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまう。
今回の両省における税制改正要望では、「土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずる」としたが、具体的な記述はない。必要な措置としては、自主的な空き家の除去等に対して一定期間、固定資産税を減免することや、除去等をしない空き家は住宅用地の軽減特例の対象から外すなどの措置が考えられ、所有者に早期撤去などを促すとみられる。
投稿者:
2014.09.17更新
【TAO通信】消費税のみなし仕入率の経過措置
2014年度税制改正において、消費税の簡易課税制度における金融業・保険業、不動産業のみなし仕入れ率が引き下げられ、2015年4月1日以後に開始する課税期間から適用されるが、その際設けられた経過措置を受けるための「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限である9月30日が迫っている。今回見直された対象業種で簡易課税の選択を考えている事業者は、早期の決断が必要になる。
簡易課税制度の見直しは、金融業及び保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種(同50%)へ、不動産業が第5種事業から新設の第6種事業(同40%)へそれぞれ変更され、みなし仕入率が現在の5区分から6区分になる。また、経過措置では、2014年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、最大2年間、旧税率が適用できる。つまり、経過措置は、2015年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用できるというものだ。
例えば、不動産業を営む3月31日決算法人が、2014年9月26日に届出書を提出した場合は2015年4月1日から2017年3月31日までの2年間が経過措置の対象となる。3月決算法人の場合は、届出書の提出は一般的に3月ごろとなるケースが多いが、経過措置を受けるためには、通常より6ヵ月早い今月末までに届出書を提出する必要があるのだ。
簡易課税制度の見直しは、金融業及び保険業が第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種(同50%)へ、不動産業が第5種事業から新設の第6種事業(同40%)へそれぞれ変更され、みなし仕入率が現在の5区分から6区分になる。また、経過措置では、2014年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、最大2年間、旧税率が適用できる。つまり、経過措置は、2015年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用できるというものだ。
例えば、不動産業を営む3月31日決算法人が、2014年9月26日に届出書を提出した場合は2015年4月1日から2017年3月31日までの2年間が経過措置の対象となる。3月決算法人の場合は、届出書の提出は一般的に3月ごろとなるケースが多いが、経過措置を受けるためには、通常より6ヵ月早い今月末までに届出書を提出する必要があるのだ。
投稿者:
2014.09.10更新
【TAO通信】NISA年間上限投資額の引き上げ案
金融庁は、NISA(少額投資非課税制度)の拡充・利便性の向上を柱とした2015年度税制改正に向けての要望を公表した。
NISAについては、(1)「ジュニアNISA(仮称)」を創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること、(2)NISAの年間上限投資額を、毎月の定額投資額に適した金額に引き上げること、(3)NISA口座開設手続き等の簡素化など、利便性を向上させること、を掲げている。
ジュニアNISAの創設については、現状のNISA利用は中高年者の投資経験者によるものが大半を占め、20代、30代の若年層は約1割にとどまっており、若年層や投資未経験者への投資家のすその拡大に資するよう、制度の拡充の必要性を指摘。年間投資上限額を80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳までは払出しを制限し、20歳になったら自動的に通常のNISAへ引き継げる仕組みを提示した。
NISAの年間上限投資額の引上げについては、野村アセットマネジメントの調査(今年2月)によると、毎月積立で活用したいという意向が約4割あり、若年層ほどその傾向が強いという結果が明らかになっている。
現行の非課税投資額は、毎年、新規投資額で100万円を上限としているが、これを毎月の定額投資額に適した金額(120万円:10万円×12ヵ月)に引き上げることを要望している。
NISAについては、(1)「ジュニアNISA(仮称)」を創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること、(2)NISAの年間上限投資額を、毎月の定額投資額に適した金額に引き上げること、(3)NISA口座開設手続き等の簡素化など、利便性を向上させること、を掲げている。
ジュニアNISAの創設については、現状のNISA利用は中高年者の投資経験者によるものが大半を占め、20代、30代の若年層は約1割にとどまっており、若年層や投資未経験者への投資家のすその拡大に資するよう、制度の拡充の必要性を指摘。年間投資上限額を80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳までは払出しを制限し、20歳になったら自動的に通常のNISAへ引き継げる仕組みを提示した。
NISAの年間上限投資額の引上げについては、野村アセットマネジメントの調査(今年2月)によると、毎月積立で活用したいという意向が約4割あり、若年層ほどその傾向が強いという結果が明らかになっている。
現行の非課税投資額は、毎年、新規投資額で100万円を上限としているが、これを毎月の定額投資額に適した金額(120万円:10万円×12ヵ月)に引き上げることを要望している。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)