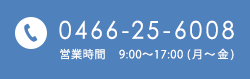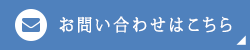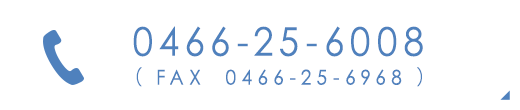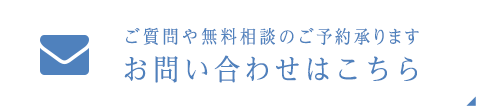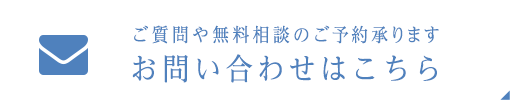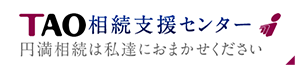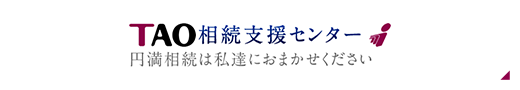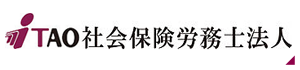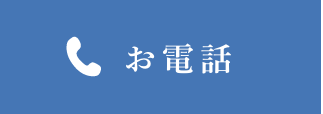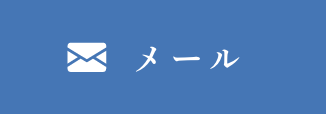経済産業省はこのほど、2014年度税制改正に関する要望を公表しました。政府・与党は、2014年度税制改正を2段階で行い、今秋にも成長戦略第2弾として設備投資減税を前倒しで実施する考えですが、経産省の税制改正要望も、(1)生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設、(2)事業再編を促進する税制の創設、などといった成長戦略関連の項目が中心となっています。
経産省は、今後3年間で国内設備投資額年間約70兆円への回復を目指しており、「生産性向上を促す設備等投資促進税制」は、先端設備の導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善など「質」の高い投資について、即時償却・税額控除等の税制措置を講じます。対象設備は、先端的な「機械・装置」に加え、生産性向上に資する「ソフトウェア」、「器具・備品」・生産ラインやオペレーションと一体となった「建物」なども対象とします。
「事業再編を促進する税制」は、自社の事業部門を切り出し、他社の事業部門と統合することで、規模の拡大や技術の補完による新市場展開・競争力強化の実現を目指す企業の課税負担の軽減措置を講じる制度の創設を求めます。
そのほか、研究開発税制の増加型上乗せ措置の控除率を現行の5%から30%に引き上げるなど拡充・延長、また、中小企業の生産性向上を促すため、中小企業投資促進税制におけるソフトウェアや関連設備等に係る特別償却率を現行の30%から即時償却に、税額控除を現行7%から12%への引上げ等の拡充を要望しています。
2013.09.04更新
【TAO通信】教育資金特例は外国国籍者も対象
2013年度税制改正において贈与税緩和の目玉として創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例は、本年4月1日から適用が始まっており、教育資金を預かる信託銀行の新サービスも順調な滑り出しをみせていますが、その適用対象者には、外国国籍者や日本国内に住所がない者も含まれることが、国税庁の通達や同通達のあらまし、財務省の2013年度税制改正の解説等で明らかになっています。
同特例は、贈与者である祖父母等の直系尊属が、受贈者である子・孫名義の口座等(教育資金口座)を金融機関に開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について子・孫ごとに1500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)までを限度として非課税とするというもの。直系尊属である贈与者と信託銀行などの金融機関との間で教育資金管理契約を締結する日において満30歳未満の受贈者が適用対象となります。
法律では、この教育資金を預かり管理する金融機関の営業所を「この法律の施行地にあるもの」と規定しているため、日本の金融機関の海外支店を含め外国に所在する金融機関では取り扱えないことになります。
このことから勘違いしがちだが、実は適用対象者については、国籍や住所に制限を設けていないことから、満30歳未満という年齢と直系尊属からの贈与という要件を満たせば、適用が受けられることになります。
同特例は、贈与者である祖父母等の直系尊属が、受贈者である子・孫名義の口座等(教育資金口座)を金融機関に開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について子・孫ごとに1500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)までを限度として非課税とするというもの。直系尊属である贈与者と信託銀行などの金融機関との間で教育資金管理契約を締結する日において満30歳未満の受贈者が適用対象となります。
法律では、この教育資金を預かり管理する金融機関の営業所を「この法律の施行地にあるもの」と規定しているため、日本の金融機関の海外支店を含め外国に所在する金融機関では取り扱えないことになります。
このことから勘違いしがちだが、実は適用対象者については、国籍や住所に制限を設けていないことから、満30歳未満という年齢と直系尊属からの贈与という要件を満たせば、適用が受けられることになります。
投稿者:
2013.08.28更新
【TAO通信】消費増税後に生活者が望む価格表示
消費税率が2014年4月から8%に引上げられた場合、商品やサービスの価格表示については、これまで法律で義務付けられていた「総額表示」(税込金額)だけでなく、条件を満たせば、「税抜価格」の表示も可能となり、様々な価格表示の可能性が出てきます。そこで、博報堂は、消費増税時の「価格表示の方法」について生活者がどのようにとらえているのかを、20~60代の男女1000人を対象に緊急調査し、速報をまとめました。
調査では、現在表示価格750円(税込)の商品について、税込表示から税抜表示まで、9つのパターンを例示し「あなたが最も良いと思うもの」を選んでもらいました。
その結果、現状で最も良いと思う表示方法は「750円(本体714円、消費税36円)」(40.1%)という「税込表示」に「本体価格」と「税額」までが記載されているトリプル表示でした。特に、税率引上げ後には支持率が48.1%と約1.2倍に増加し、その傾向が強まっています。
次いで、「750円(うち消費税36円)」(現状17.7%、税率引上げ後18.8%)、「750円(税込)」(同16.5%、同11.9%)、「750円(本体価格714円)」(同16.4%、同13.6%)といった、「税込表示」をメインに「本体価格」、「税額」も補助的に表示されるものが支持されています。
一方で、「税抜714円+税」や「714円 税抜」、「税抜714円 税36円」といった税抜表示は、現状で計0.7%、引上げ後も計約2%程度と非常に少ない結果となりました。
調査では、現在表示価格750円(税込)の商品について、税込表示から税抜表示まで、9つのパターンを例示し「あなたが最も良いと思うもの」を選んでもらいました。
その結果、現状で最も良いと思う表示方法は「750円(本体714円、消費税36円)」(40.1%)という「税込表示」に「本体価格」と「税額」までが記載されているトリプル表示でした。特に、税率引上げ後には支持率が48.1%と約1.2倍に増加し、その傾向が強まっています。
次いで、「750円(うち消費税36円)」(現状17.7%、税率引上げ後18.8%)、「750円(税込)」(同16.5%、同11.9%)、「750円(本体価格714円)」(同16.4%、同13.6%)といった、「税込表示」をメインに「本体価格」、「税額」も補助的に表示されるものが支持されています。
一方で、「税抜714円+税」や「714円 税抜」、「税抜714円 税36円」といった税抜表示は、現状で計0.7%、引上げ後も計約2%程度と非常に少ない結果となりました。
投稿者:
2013.08.21更新
【TAO通信】1千兆円を突破した国の借金
財務省が公表した2013年6月末時点での国債や借入金などを合計した「国の借金」は1008兆6281億円となり、過去最大を更新した2012年12月末時点(997兆2181億円)を11兆4100億円上回り、とうとう1千兆円の大台を突破しました。もともと、地方が抱える長期債務残高(2012年度末で約201兆円程度の見込み)を合わせれば1千兆円を超えていましたが、国の借金分だけで大台を超える状況となりました。
2012年度末の3月に比べ、国債は約9兆円増の約830.5兆円で全体の約82%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.3兆円増の約716.4兆円(うち復興債が約11兆円)と過去最高となりました。
この「国の借金」1008兆6281億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約23倍。年収500万円のサラリーマンが1億1700万円の借金を抱えている勘定です。
また、わが国の今年7月1日時点での推計人口1億2735万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、今年3月末時点の約779万円から約792万円に上昇します。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(当初予算ベース)の公債残高は、2013年6月末実績での約716兆円から約750兆円程度に膨らむと見込まれています。これは、2013年度一般会計税収予算額約43兆円の約17年分に相当し、将来世代に大きな負担を残すことになります。
2012年度末の3月に比べ、国債は約9兆円増の約830.5兆円で全体の約82%を占め、うち普通国債(建設国債+赤字国債)は、約11.3兆円増の約716.4兆円(うち復興債が約11兆円)と過去最高となりました。
この「国の借金」1008兆6281億円は、2013年度一般会計提出予算の歳出総額92兆6115億円の約11倍、同年度税収見込み額43兆960億円の約23倍。年収500万円のサラリーマンが1億1700万円の借金を抱えている勘定です。
また、わが国の今年7月1日時点での推計人口1億2735万人(総務省統計、概算値)で割ると、国民1人当たりの借金は、今年3月末時点の約779万円から約792万円に上昇します。
わが国の公債残高(普通国債残高)は年々増加の一途を辿っており、2013年度末(当初予算ベース)の公債残高は、2013年6月末実績での約716兆円から約750兆円程度に膨らむと見込まれています。これは、2013年度一般会計税収予算額約43兆円の約17年分に相当し、将来世代に大きな負担を残すことになります。
投稿者:
2013.08.07更新
【TAO通信】消費増税時の広告等の指針案公表
消費者庁は、2014年4月の消費増税時のセール表示等に関する指針案を公表し、「事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことを禁止するもの」との考えを示しました。
禁止表示の具体例として、「消費税は転嫁しません」「消費税率上昇分値引きします」「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などを挙げています。ただし、「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されません。
「消費税」の文言を含まない表現は、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、原則容認されます。しかし、「消費税」の文言を含まない表現でも、例えば、「増税分3%値下げ」や「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」や「税」といった文言を使って実質的に消費増税分を値引きするなどの趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止する表示に該当します。一方、宣伝や広告の表示全体からみて、消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、いずれも、消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当しません。具体例として、(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」、(2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、を挙げています。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。
禁止表示の具体例として、「消費税は転嫁しません」「消費税率上昇分値引きします」「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」などを挙げています。ただし、「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されません。
「消費税」の文言を含まない表現は、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、原則容認されます。しかし、「消費税」の文言を含まない表現でも、例えば、「増税分3%値下げ」や「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」や「税」といった文言を使って実質的に消費増税分を値引きするなどの趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止する表示に該当します。一方、宣伝や広告の表示全体からみて、消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、いずれも、消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当しません。具体例として、(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」、(2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、を挙げています。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。
投稿者:
2013.07.31更新
【TAO通信】社員にかけた生命保険のトラブル
経営戦略の一環として、会社が契約者、役員や従業員を被保険者及び保険金受取人とする養老保険に加入するケースがあります。この場合、死亡保険金も満期保険金も受取人が被保険者(またはその遺族)となっていることから、会社が負担した保険料は、被保険者である役員及び従業員への給与扱いとなります。
被保険者が役員の場合の支払保険料相当額は、保険料を毎月または毎年一定額ずつ支払うことで「定期同額給与」とみなされれば、損金算入扱いとなります。支払保険料を損金に算入しながら、退職金の原資作りや「もしも」の場合の保障をカバーできることになります。
しかし、満期や死亡などの保険事故が発生する前にこの契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐってトラブルにならないよう注意が必要となります。被保険者である役員や従業員にしてみれば、このタイプの保険契約は、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるということになり決して悪い話ではありません。ただし、何らかの事情でこの契約を会社が解約した場合には少し微妙な状況になってきます。
解約返戻金は原則として契約者に帰属するため、会社に支払われます。支払われた解約返戻金を会社が役員や従業員のために使うのであればまだいいが、全く関係ない使われ方をされた場合、それまで給与課税されてきた役員や従業員などの被保険者は"取られ損"になってしまうわけです。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。
被保険者が役員の場合の支払保険料相当額は、保険料を毎月または毎年一定額ずつ支払うことで「定期同額給与」とみなされれば、損金算入扱いとなります。支払保険料を損金に算入しながら、退職金の原資作りや「もしも」の場合の保障をカバーできることになります。
しかし、満期や死亡などの保険事故が発生する前にこの契約を解約する場合には、解約返戻金をめぐってトラブルにならないよう注意が必要となります。被保険者である役員や従業員にしてみれば、このタイプの保険契約は、給与課税分の負担だけで生命保険に加入できるということになり決して悪い話ではありません。ただし、何らかの事情でこの契約を会社が解約した場合には少し微妙な状況になってきます。
解約返戻金は原則として契約者に帰属するため、会社に支払われます。支払われた解約返戻金を会社が役員や従業員のために使うのであればまだいいが、全く関係ない使われ方をされた場合、それまで給与課税されてきた役員や従業員などの被保険者は"取られ損"になってしまうわけです。「話が違うじゃないか」と司法トラブルに発展しないよう、十分な配慮が必要となります。
投稿者:
2013.07.24更新
【TAO通信】2013年度税制改正で法基通を公表
国税庁はこのほど、2013年度税制改正に関連して、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表し、同年度改正で創設された生産等設備投資促進税制について、法律等で規定されていなかった生産等設備の範囲を明確にしました。また、生産等設備には該当しない本店と該当する店舗を一棟の建物で共用する「共用資産」は、全てが生産等設備に該当することを明らかにしています。
通達によると、生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗、自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(生産等活動)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎棟の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、該当しないとして生産等設備の範囲を明確化しました。
さらに、一棟の建物が本店用と店舗用に共用される場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されるもの(共用資産)については、その全てが生産等設備になることを併せて明らかにしました。また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分に合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算することを認めることを明らかにしています。
通達によると、生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗、自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(生産等活動)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、本店、寄宿舎棟の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設のようなものは、該当しないとして生産等設備の範囲を明確化しました。
さらに、一棟の建物が本店用と店舗用に共用される場合など、減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されるもの(共用資産)については、その全てが生産等設備になることを併せて明らかにしました。また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分に合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算することを認めることを明らかにしています。
投稿者:
2013.07.17更新
【TAO通信】消費税引上げ時の住宅購入に補助
自民・公明両党は、住宅取得に係る消費税の負担増を軽減するため、消費税率引上げ時に現金による給付措置を実施する方針を固めました。
具体的には、消費税率が8%に引き上げられる2014年4月以後の住宅ローン利用の購入者には、年収510万円以下を対象に現金10万円~30万円を給付。10%引上げ時の2015年10月以後は、年収775万円以下を対象に現金10万円~50万円を給付します。これらは住宅ローン減税と合わせて適用されます。
一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けた上で現金による給付を行います。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給します。
住宅は取引価格が高額なため消費税率引上げの影響が大きく、税率引上げ後の住宅需要の冷え込みが予想されることから、2013年度税制改正では、本年末で期限が切れる住宅ローン減税や自己資金での住宅購入者に対する減税を拡充しました。
ただし、所得税・住民税額が減税による控除額に満たない所得層は減税の恩恵を充分に受けられないという問題があったため、2013年度税制改正大綱では、この層に対しては減税措置と併せ特例的な給付措置を行うことにより、消費税負担増を緩和するとし、給付措置の具体的な内容をこの夏までに示すとしていましたが、このほど、ようやくその給付措置の概要が明らかになりました。
具体的には、消費税率が8%に引き上げられる2014年4月以後の住宅ローン利用の購入者には、年収510万円以下を対象に現金10万円~30万円を給付。10%引上げ時の2015年10月以後は、年収775万円以下を対象に現金10万円~50万円を給付します。これらは住宅ローン減税と合わせて適用されます。
一方、自己資金での住宅購入者には年収要件に加え年齢制限も設けた上で現金による給付を行います。50歳以上、年収650万円以下を対象に、8%時に最大30万円、10%時に最大50万円を支給します。
住宅は取引価格が高額なため消費税率引上げの影響が大きく、税率引上げ後の住宅需要の冷え込みが予想されることから、2013年度税制改正では、本年末で期限が切れる住宅ローン減税や自己資金での住宅購入者に対する減税を拡充しました。
ただし、所得税・住民税額が減税による控除額に満たない所得層は減税の恩恵を充分に受けられないという問題があったため、2013年度税制改正大綱では、この層に対しては減税措置と併せ特例的な給付措置を行うことにより、消費税負担増を緩和するとし、給付措置の具体的な内容をこの夏までに示すとしていましたが、このほど、ようやくその給付措置の概要が明らかになりました。
投稿者:
2013.07.10更新
【TAO通信】2013年分路線価
全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2013年分の路線価及び評価倍率が公表されました。今年1月1日時点の全国約35万6千地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は1.8%下落し、5年連続の下落となりました。
しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分以降は3.1%→2.8%→1.8%と確実に下落状況に落着きが出てきています。
都道府県別の路線価をみると、昨年分は全ての都道府県で下落しましたが、今年分は宮城(+1.7%)・愛知(+0.1%)の2県で上昇。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の35都道府県から41都道府県に増え、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年の12都道府県から4都道府県(青森、秋田、徳島、高知)へと大幅に減少しました。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の2都市から7都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ8都市、最高路線価が下落した都市は昨年の37都市から32都市に減少しました。このうち上昇率「5%以上」の都市は、横浜、金沢、那覇、上昇率「5%未満」の都市は、札幌、さいたま、名古屋、大阪となっており、地価の下げ止まり傾向が地方の中心都市にも広がりつつあります。都道府県庁所在都市の最高路線価では、東京・中央区銀座5丁目の「銀座中央通り」が、1平方メートルあたり2152万円で、28年連続の全国トップとなりました。
しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分以降は3.1%→2.8%→1.8%と確実に下落状況に落着きが出てきています。
都道府県別の路線価をみると、昨年分は全ての都道府県で下落しましたが、今年分は宮城(+1.7%)・愛知(+0.1%)の2県で上昇。下落率が「5%未満」の都道府県は昨年の35都道府県から41都道府県に増え、下落率が「5%以上」の都道府県は昨年の12都道府県から4都道府県(青森、秋田、徳島、高知)へと大幅に減少しました。
一方、都道府県庁所在都市の最高路線価が上昇した都市は昨年の2都市から7都市に増え、横ばいの都市は昨年と同じ8都市、最高路線価が下落した都市は昨年の37都市から32都市に減少しました。このうち上昇率「5%以上」の都市は、横浜、金沢、那覇、上昇率「5%未満」の都市は、札幌、さいたま、名古屋、大阪となっており、地価の下げ止まり傾向が地方の中心都市にも広がりつつあります。都道府県庁所在都市の最高路線価では、東京・中央区銀座5丁目の「銀座中央通り」が、1平方メートルあたり2152万円で、28年連続の全国トップとなりました。
投稿者:
2013.07.03更新
【TAO通信】12年度査察の脱税総額は205億円
いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調査され検察当局に告発されて刑事罰の対象となります。
国税庁がこのほど公表した2012年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より5件少ない190件、脱税総額は平成以降最低だった前年度を約13億円上回る約205億円と低水準が続いています。1件当たりでは同500万円多い1億700万円。検察庁に告発した件数は同12件多い129件でした。
今年3月までの1年間に、全国の国税局が査察に着手した件数は190件と、42年ぶりの低水準となりました。継続事案を含む191件を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち67.5%にあたる129件を検察庁に告発しました。
この告発率67.5%は、前年度を5.6ポイント上回るが、前年度(61.9%)は38年ぶりの低水準だったもので、高い割合ではありません。告発事件のうち、脱税額(加算税を含む)が3億円以上のものは11件、脱税額が5億円以上のものは3件でした。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあることから、2012年度の脱税総額205億円は、ピークの1988年度(714億円)の約29%にまで減少しました。
告発分の脱税総額は前年度を約18億円上回る約175億円、1件あたり平均の脱税額は1億3500万円でした。 告発件数の多かった業種・取引は、「情報提供サービス業」が11件、「クラブ・バー」がともに11件トップ、「建設業」が7件で続いています。
国税庁がこのほど公表した2012年度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件は前年度より5件少ない190件、脱税総額は平成以降最低だった前年度を約13億円上回る約205億円と低水準が続いています。1件当たりでは同500万円多い1億700万円。検察庁に告発した件数は同12件多い129件でした。
今年3月までの1年間に、全国の国税局が査察に着手した件数は190件と、42年ぶりの低水準となりました。継続事案を含む191件を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、うち67.5%にあたる129件を検察庁に告発しました。
この告発率67.5%は、前年度を5.6ポイント上回るが、前年度(61.9%)は38年ぶりの低水準だったもので、高い割合ではありません。告発事件のうち、脱税額(加算税を含む)が3億円以上のものは11件、脱税額が5億円以上のものは3件でした。近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあることから、2012年度の脱税総額205億円は、ピークの1988年度(714億円)の約29%にまで減少しました。
告発分の脱税総額は前年度を約18億円上回る約175億円、1件あたり平均の脱税額は1億3500万円でした。 告発件数の多かった業種・取引は、「情報提供サービス業」が11件、「クラブ・バー」がともに11件トップ、「建設業」が7件で続いています。
投稿者:
SEARCH
ARCHIVE
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年01月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年01月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年04月 (1)
- 2022年01月 (3)
- 2021年12月 (1)
- 2021年09月 (1)
- 2021年08月 (1)
- 2021年07月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年06月 (1)
- 2020年01月 (1)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (1)
- 2019年09月 (1)
- 2019年08月 (1)
- 2019年06月 (1)
- 2019年04月 (2)
- 2019年02月 (2)
- 2019年01月 (2)
- 2018年10月 (1)
- 2018年08月 (1)
- 2018年07月 (2)
- 2018年05月 (1)
- 2018年03月 (1)
- 2018年02月 (1)
- 2016年07月 (5)
- 2016年06月 (5)
- 2016年05月 (4)
- 2016年04月 (5)
- 2016年03月 (5)
- 2016年02月 (4)
- 2016年01月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年09月 (6)
- 2015年08月 (3)
- 2015年07月 (7)
- 2015年06月 (4)
- 2015年05月 (3)
- 2015年04月 (5)
- 2015年03月 (4)
- 2015年02月 (4)
- 2015年01月 (2)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年09月 (3)
- 2014年08月 (4)
- 2014年07月 (5)
- 2014年06月 (4)
- 2014年05月 (5)
- 2014年04月 (5)
- 2014年03月 (4)
- 2014年02月 (4)
- 2014年01月 (3)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (5)
- 2013年09月 (4)
- 2013年08月 (3)
- 2013年07月 (5)
- 2013年06月 (4)
- 2013年05月 (5)
- 2013年04月 (4)
- 2013年03月 (8)
- 2013年02月 (8)
- 2013年01月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (12)
- 2012年09月 (8)
- 2012年08月 (8)
- 2012年07月 (8)
- 2012年06月 (6)
- 2012年05月 (10)
- 2012年04月 (8)
- 2012年03月 (6)
- 2012年02月 (8)
- 2012年01月 (4)
- 2011年12月 (1)