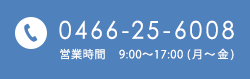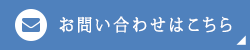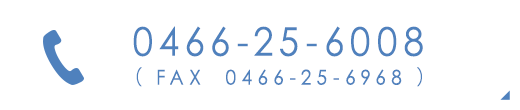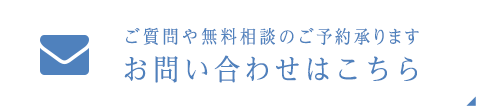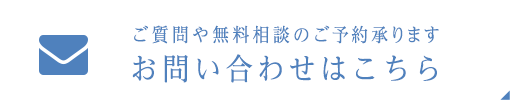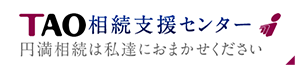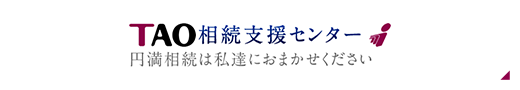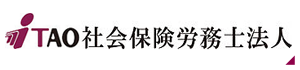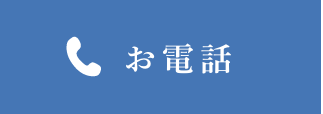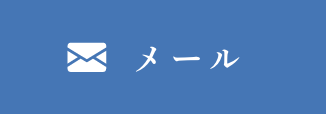2019年10月からの消費税率10%への引上げに伴い、賃貸借、リース、請負などの契約については、施行日 (10月1日)の半年前となる4月1日を指定日として、その前日の3月31日までの契約であれば、施行日以後の引渡し等であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。
1.賃貸借・リース契約の経過措置の対象となる契約とは
経過措置の適用対象となる資産の貸付け等に係る契約は、次の①と②、又は①と③の要件を満たすものに限られます。
① 貸付期間とその期間中の対価の額が契約で定められていること
② 事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと
家賃については、「家賃の改定協議可能」を旨とする文言が契約書に記載されているケースが多く、その場合は、上記の要件を満たさず、施行日以後は、10%の消費税率が適用されます。
2.請負契約の対象となる契約とは
経過措置の対象となる請負契約は、2019年3月31日までに契約した工事・製造に係る請負契約の他、「一定の要件」に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等の請負契約が含まれます。「一定の要件」とは、次のとおりです。
① 仕事の性質上、完成に長期間を要するものであること
② 仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの、または目的物の引渡しを要しない請負の場合は、約した役務の全部の完了が一括して行われるもの
③ 上記①、②の要件を満たし、その内容について相手方の注文があること
3.建築請負等でよくある実務上の注意点
(1) 2019年9月末完成予定が10月以後に延びてしまった場合
2019年4月以後の契約で、9月30日までに引渡し予定の小規模工事が、何らかの事情で工事が伸びて、引渡しが10月1日以後になった場合、10%の税率を適用しなければなりません。このような事態に備えて、あらかじめ、契約書等には「引渡しが10月1日以後になる場合は10%の税率が適用される」旨の一文を加えておきましょう。
(2)受注した工事を下請会社に発注する場合
経過措置は、発注者と建築業者との請負契約のみならず、その建築業者と下請業者との間の契約についても適用されます。2019年3月末間際の契約で、次のような場合は注意が必要です。
① 発注者と建築業者との契約は経過措置の対象として8%の消費税率が適用される。
② この建築業者と下請業者との請負契約の締結が、指定日の4月1日以後になってしまった場合には、経過措置の対象とならず、10%の消費税率が適用される。