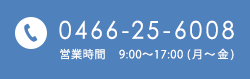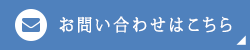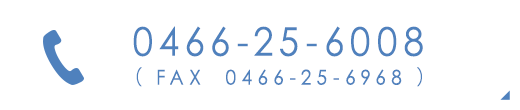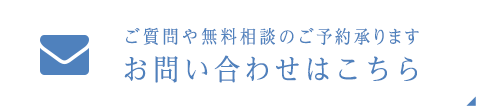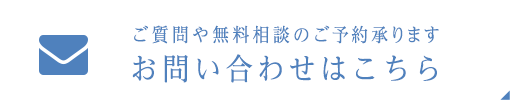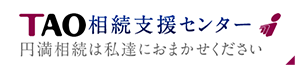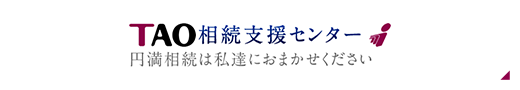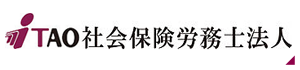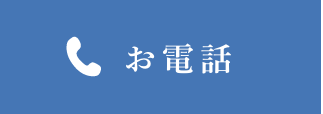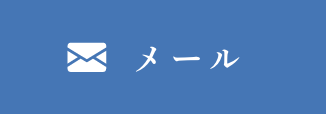先日、あるお客様との会話の中で「三方よし」という言葉が出てきました。「三方よし」、みなさんはご存知でしょうか。
「三方よし」とは、江戸時代から明治時代にかけて活躍した近江国(現在の滋賀県)出身の商人である近江商人の商売理念で、「売り手よし 買い手よし 世間よし」というものです。企業は利益を追求するために事業を行っているわけですが、単に自社の利益のみを追い求めればいいというものではなく、お客様や社会全体を幸せにするものでなくてはなりません。利益至上主義に走れば短期的には利益はあがるかもしれませんが、長期的にはこの「三方よし」の理念で経営することが企業に永続的な繁栄をもたらすのだと思います。
さらに、近江商人は「商売十訓」という商売心得も記しており、私自身、大変腑に落ちるものがありましたので、ここで紹介させていただきます。
1 商売は世の為、人の為の奉仕にして、利益はその当然の報酬なり
2 店の大小よりも場所の良否、場所の良否よりも品の如何
3 売る前のお世辞より売った後の奉仕、これこそ永遠の客をつくる
4 資金の少なきを憂うなかれ、信用の足らざるを憂うべし
5 無理に売るな、客の好むものも売るな、客の為になるものを売れ
6 良きものを売るは善なり、良き品を広告して多く売ることはさらに善なり
7 紙一枚でも景品はお客を喜ばせる、つけてあげるもののないとき笑顔を景品にせよ
8 正札を守れ、値引きは却って気持ちを悪くするくらいが落ちだ
9 今日の損益を常に考えよ、今日の損益を明らかにしないでは、寝につかぬ習慣にせよ
10 商売には好況、不況はない、いずれにしても儲けねばならぬ
いかがでしょう、いずれもシンプルなことですが、まさにビジネスの本質をついていると思いませんか。当たり前のことを当たり前にやる、これは言うは易し行うは難しです。当たり前のことを徹底してやれれば、それだけで十分他社と差別化は図れるのだと思います。
「温故知新」「不易流行」などの言葉のとおり、どれだけ時代が変わろうとも基本とすべきことは軸に据えながら、その上に新しいものを取り入れていくということが商売の本質と言えるのではないでしょうか。先行き不透明な時代だからこそ、商売の原点に立ち戻ってみるのも必要なことかもしれません。
(S.H)