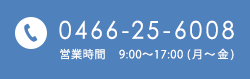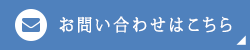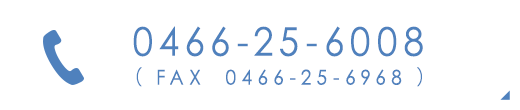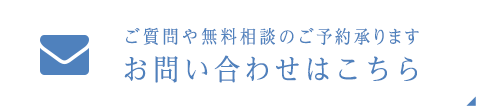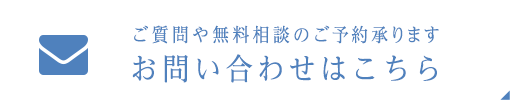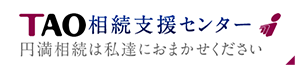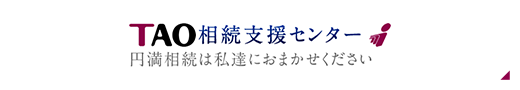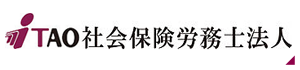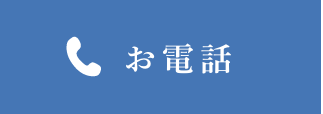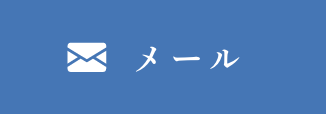約40年ぶりの民法改正により相続税の改正が行われます。
いくつか例をあげてみます。
1.口座の凍結(預貯金関係)
今までは遺産分割協議が終わるまで被相続人(故人)の銀行口座は凍結(引出等ができない)されていましたが、改正により相続人であれば死亡時の預貯金額×3分の1×法定相続分を引き出すことができるようになりました。
ただし一つの金融機関から引き出せる上限は150万円までです。
1.遺留分が金銭で解決される
遺留分の侵害額の請求について、現金での支払いが原則という変更がなされました。
遺留分とは、法定相続分とは別に、最低保障される取り分のこと。
1.特別の寄与
たとえば、これまで(被相続人の)長男の妻が夫の両親の介護に尽くしても相続人ではないので、妻は一切の相続はできませんでした。
改正後は特別の寄与として、妻も遺産を受け取る権利が発生する。相続人対し、寄与に応じた請求をすることができるようになりました。
ただし、被相続人の財産の維持等に多大な貢献をした場合という厳しい条件があります。
(T.Y)